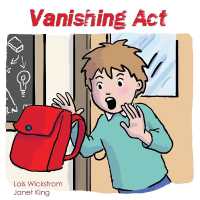- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日本の相対的貧困率15%、資産5億円以上9万世帯。アダム・スミスからピケティまで格差と経済学の歴史を辿り、日本の道を考える。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
129
民主主義が進み貧困層も政治に参加すると、貧富の格差是正を考える学問として経済学が発展した。欧州では福祉国家化が一応の成果を上げたが、強制的な平等実現を唱えたマルクス経済学はソ連崩壊で失敗し、新自由主義の台頭で格差は一層顕著となった。格差問題と対峙してきた経済学の歴史を俯瞰し、成長と公平性が両立する政策を提案する。最低賃金上昇や高齢者雇用拡大など一部は実現しているが、強力な既得権益の突破なくして根本的な改革は無理な点に言及していない。自由が前提の資本主義で強い権力の問題を考えねばならない時期が近付いている。2024/08/04
trazom
128
格差の経済学の第一人者である橘木先生(先生のことを「日本のピケティ」と言う人がいるが、何と無礼。ピケティ博士を「フランスの橘木」と呼べ!)。格差に対応した経済学説の歴史や、各国の政策の違いがよくわかる。比較的平等社会と思っていた日本だが、相対的貧困率がG7の中で最悪(アメリカより悪い!)にはショック。福祉の提供は家族・親族という歴史的背景が、政治の対応を遅らせたのだろうか。格差問題は「経済成長(効率性)か公平性(平等性)か」というトレードオフが全てだという。その双方を失っている日本の惨状が浮き彫りになる。2024/06/26
1.3manen
56
貧困の経済学―ブースとラウントリー。ミュルダールはスウェーデン人で、経済政策や社会政策の運営に政府の役割を重視した(94頁)。ケインズと類似。ピケティはアメリカの所得税率では累進度の弱いことを批判し、強化を求めるが、クルーグマンは100%賛意を表明(126頁)。野村総研(2021)の階層別金融資産額と世帯数では、超富裕層は5億円以上105兆円(9.0万世帯、156頁)。橘木先生は、貧困層下位10%、下位1%の人を無視しているのが気になるという。2024/08/08
よっち
31
日本では資産5億円以上の超富裕層は9万世帯。単身世帯の34・5%は資産ゼロ。経済学の歴史に学びながら、経済成長か格差是正か、資本主義のジレンマや今後の進むべき道を考える1冊。富裕者をより富ませ、貧困者をより貧しくさせる今日の資本主義。アダム・スミスやマルクス、ケインズ、そしてピケティは「富と貧困」の問題をいかに論じてきたか。数値をもとに今の日本の貧困を考えながら、転機となった経済理論や歴史的な経緯を踏まえつつ、ピケティによる高所得者の動向分析や各国の動向を紹介して、ざっと概況を学べる1冊になっていました。2024/06/04
Satoshi
15
2000年代初頭から格差を研究していた著者による経済史の解説本。マルクスからリバタリアニズムまで総ざらいしている。印象に残ったことは巷に流布されている累進課税は資本家のモチベーションを低下させるとか福祉国家は競争力を落とすという論説は明確な根拠のないものであり、1970年代の日本の累進課税率が最も公平な課税であったという研究結果がある。レーガンとサッチャーの路線をグローバルスタンダードとしたことに誤りがあるのではと思ってしまった。2024/12/29
-

- 電子書籍
- 蒼穹の剣【タテヨミ】第299話 pic…
-
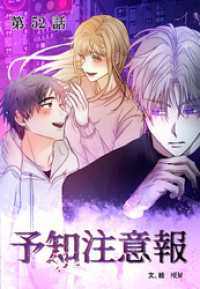
- 電子書籍
- 予知注意報【タテマンガ】第52話 YU…
-
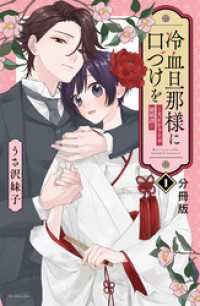
- 電子書籍
- 冷血旦那様に口づけを~大正かりそめ婚姻…
-
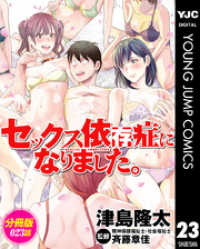
- 電子書籍
- セックス依存症になりました。 分冊版 …