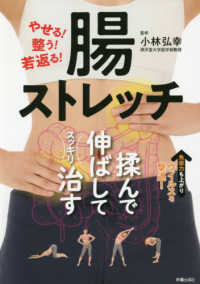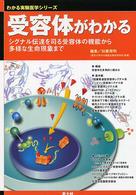内容説明
身体全体がふくれあがるような日々だった。ふれるものすべてに問題を発見し、ぎりぎり集中して行った。――一九五九年に本島、久高島、宮古島、石垣島、竹富島、そして六六年に久高島を再訪。沖縄に恋をした芸術家が見た舞踊、歌、そして神事からの日本再発見。毎日出版文化賞受賞作。著者撮影による写真口絵六四ページを収録。
〈随筆〉岡本敏子
〈解説〉外間守善/赤坂憲雄
(目次より)
沖縄の肌ざわり
「何もないこと」の眩暈
八重山の悲歌
踊る島
神と木と石
ちゅらかさの伝統
結 語
増補
神々の島 久高島
本土復帰にあたって
あとがき
「一つの恋」の証言者として岡本敏子
新版に寄せて 岡本太郎の『沖縄文化論』を読む外間守善
解説赤坂憲雄
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ishii.mg
2
イザイホーがあり、風葬がのこり、ソテツを食らう飢餓を目の当たりにする、そんな時代の沖縄を天才芸術家と民俗学の視点から、万感の愛情と冷徹な観察で記述した名作傑作。2024/09/14
kaz
2
写真を中心に飛ばし読み。やはりアングルが違う。図書館の内容紹介は『身体全体がふくれあがるような日々だった-。1959年と1966年、沖縄に恋をした芸術家・岡本太郎の日本再発見の旅の記録。著者撮影の写真76点、岡本敏子、外間守善らによる解説も収録する』。 2024/06/04
ソフィ
1
厳しい。鋭い。でもとことん本質。今だったら真意をつかみかねる人々からバッシングされてしまいかねない内容だけに、こうして文字で残してくれてありがたいと感じる。「美しいものではあっても、美しいと言わない。そう表現してはならないところにこの文化の本質がある。」「……凝視される対象となったとたん、その実態を喪失してしまうような、そこに私のつきとめたい生命の感動を見とるのだ」。2025/10/26
mikoto_oji
1
改めて岡本太郎の凄味を感じる。岡本太郎がメディアに露出していた頃は、まだ幼く変な人くらいに思っていたが年を経て才能の素晴らしさを人間としての魅力を思いしらされています。この本では、民俗学者としての顔を見せ、素晴らしい文章を綴っている。2025/05/31
ヤエガシ
1
岡本太郎は、本書の中で中国、朝鮮、日本の文化が混合してできた沖縄の人工物的な文化について「外来物の適当な綜合」と、あまり関心を示さず、むしろ自然と密接に関係していて、原始日本の文化の名残りがある、人々の踊り、神事、埋葬習慣などに、惹きつけられていて、世界的な芸術家なのに「そっちに関心行くのか」と意外だったんですが、解説によると岡本太郎はソルボンヌ大学でオセアニアの民俗学を専攻されていたそうで、実は「そっち」の専門家でもあったと知って、多才さに驚きました。2025/01/02
-
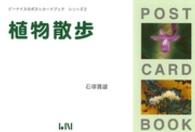
- 電子書籍
- 植物散歩 ポストカードブックシリーズ