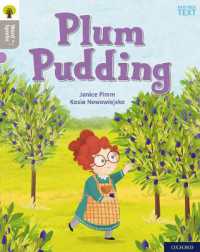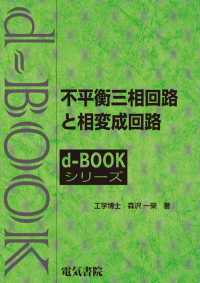内容説明
第二次世界大戦後、ナチ・ドイツから解放されたフランスの思想界には、時代を牽引する書き手が台頭した。サルトルを筆頭にカミュやボーヴォワール、メルロ=ポンティ、バタイユらが次々と作品を世に問い、論戦も繰り広げた。本書は、哲学と文学を架橋して展開された彼らの創作活動に着目。実存主義が世を席巻し、知識人や芸術家の政治的社会参加(アンガジュマン)が唱えられた時代の知的潮流は、何をもたらしたのか。その内実を描き出す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
118
割と、わかりやすく面白い。 デリダがメルロポンティの文を難解だ、と言ったとか、バタイユがマーシャルプランを褒めたたえた文でノーベル平和賞期待した、とか、哲学オタク用笑いのネタも所々仕込んである。2024/08/01
Ex libris 毒餃子
14
戦後フランス思想のうちでも、サルトルとの絡みがある者にフォーカスを当てている本。哲学と文学を行ったり来たりしながら、サルトルの哲学とどのように影響しあっているかをメインにしてカミュ、ボーヴォワール、メルロポンティ、バタイユを紹介している。フォーカスの仕方で思想の見え方が違ってくるのがわかるのが、他の戦後フランス思想との違いかなぁ、という印象。2024/05/06
ラウリスタ~
13
サルトル、カミュ、ボーヴォワール、メルト=ポンティ、バタイユ、そして彼らの間での論争や諍いについて。個々の作家、哲学者の思想の内容に深入りするというよりも、第二次大戦の惨禍に呆然とするフランスで、彼らがいかに「歴史」と立ち向かっていったのか(マルクス主義との関わりなど)。戦後のサルトルはマルクス主義的な歴史推進のための投企に邁進し、目的が手段を正当化しているとのカミュらからの批判に対し、日和見的だと反駁。今から見ればサルトルが間違っているし、反米、親ソの運動家としてのサルトルはちょっと偏狭に見える。2024/06/14
ネムル
9
反米親ソのサルトルは結果的に間違っていたとは、ひとまず歴史的にケリをつけてしまうことは出来るが、それでもなおなぜ運動家としてのサルトルに惹かれてしまうのかという謎が提示されている。アジテーターとしての側面には苦手意識があるなと思うが。2024/05/19
つまみ食い
7
サルトル、カミュ、ボーヴォワール、バタイユ、メルロ=ポンティらのそれぞれの思想と関係が整理されている。新書サイズでまとまっているので、手元に置けるガイドとして有用2024/09/05
-
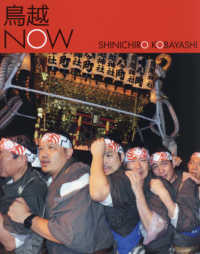
- 和書
- 鳥越NOW