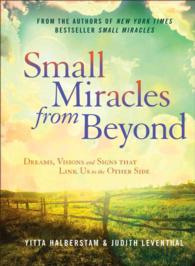内容説明
市場化による公立学校の序列化と教育格差の拡大.規制緩和で使い捨て労働者と化す教員.企業が公教育をターゲットにあらゆる領域で肥え太っていく――.新自由主義の極限にあるアメリカの現実とは.そしてPISAに見られる教育の数値化・標準化の危険性とは.ニューヨーク在住の気鋭の研究者が,近未来の日本に警鐘を鳴らす.
目次
はじめに──日本人が知らないアメリカの教育の闇
第1章 教育を市場化した新自由主義改革
第2章 企業の企業による企業のための教育改革
第3章 市場型学校選択制と失われゆく「公」教育
第4章 発展途上国からの「教員輸入」と使い捨て教員
第5章 PISAと教育の数値化、標準化、そして商品化
第6章 アメリカのゼロ・トレランスと教育の特権化
第7章 アカウンタビリティという新自由主義的な「責任」の形
第8章 「プロ教師」育成の落とし穴──「生かす」というパラダイムシフト
第9章 シカゴ教員組合ストライキ──組合改革から公教育の「公」を取り戻す市民運動へ
第10章 立ち上がったアメリカの人々
おわりに──三人の先生
あとがき
注
キーワード(電子版付録)
-
- 洋書
- Scissorman