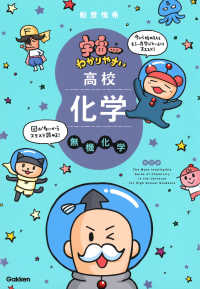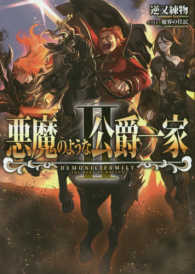内容説明
「訂正可能性の哲学」がケアの哲学だったことを、本書を読んで知った。
ケアとは、あらゆる関係のたえざる訂正のことなのだ。
──東浩紀
人と出会い直し、つながりを結び直すために。
「大切にしているもの」をめぐる哲学論考。
「僕たちは、ケア抜きには生きていけなくなった種である」
多様性の時代となり、大切にしているものが一人ひとりズレる社会で、善意を空転させることもなく、人を傷つけることもなく、生きていくにはどうしたらいいのか? 人と出会い直し、歩み直し、関係を結び直すための、利他とは何か、ケアの本質とは何かについての哲学的考察。
進化生物学、ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」、スラヴォイ・ジジェクの哲学、宇沢弘文の社会的費用論、さらには遠藤周作、深沢七郎、サン=テグジュペリ、村上春樹などの文学作品をもとに考察する、書きおろしケア論。『楢山節考』はセルフケアの物語だった!
「大切なものはどこにあるのか? と問えば、その人の心の中あるいは記憶の中という、外部の人間からはアクセスできない「箱」の中に入っている、というのが僕らの常識的描像と言えるでしょう。/ですが、これは本当なのでしょうか?/むしろ、僕らが素朴に抱いている「心という描像」あるいは「心のイメージ」のほうが間違っているという可能性は?/この本では哲学者ウィトゲンシュタインが提示した議論、比喩、アナロジーを援用してその方向性を語っていきます。」(まえがきより)
【目次】
まえがき──独りよがりな善意の空回りという問題
第1章 多様性の時代におけるケアの必然性
第2章 利他とケア
第3章 不合理であるからこそ信じる
第4章 心は隠されている?
第5章 大切なものは「箱の中」には入っていない
第6章 言語ゲームと「だったことになる」という形式
第7章 利他とは、相手を変えようとするのではなく、自分が変わること
第8章 有機体と、傷という運命
終章 新しい劇の始まりを待つ、祈る
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コットン
エジー@中小企業診断士
ta_chanko
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
つゆ