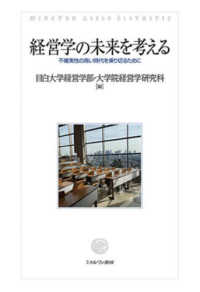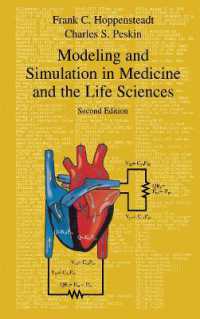内容説明
古来、人びとは気候変動にどのように適応してきたのか。近年、急速に発展している年単位での古気候の復元研究で明らかにされた最新データと史資料を照らし合わせて、数年・数十年・数百年周期の気候変化のスピードが、いかに社会に影響を与えたかという視点で描く初めての通史。昨今の地球環境問題を考えるうえで、気候適応史研究の重要性を説く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
109
人は自然環境と関わって歴史を創ってきたが、その環境には気候も含まれる。気候変動で飢餓に襲われ、住みやすい土地に移住する例は今日も珍しくない。気候の変化に人が適応していくプロセスを古気候復元によるデータから検証するという、従来の歴史学にはない理系の視点に考えさせられる。寒冷期の凶作で朝鮮半島の水田耕作者が日本へ移り、平家没落は気象災害による問題噴出の責任を取らされた結果など初めて聞く指摘だ。グラフや気象学の論考も多く文系には難しいが、温暖化への対応が国際的課題とされる現代だからこそ過去の再検証は必要だろう。2022/09/10
六点
90
著者略歴で「京都大学理学部卒」とあり、「しまった、これは敵(何のだ)の罠に御座る」と叫びたくなった。それは、ともかく、歴史学的なタイムスパンに於いて、長期・中期・短期の3種類の指標が用いられている。この本では特に、最近作られた「年輪酸素同位体気候成分」により過去2600年分という長期に渡る1年毎のデータ編年が完成した。その解析(過去の文献に於ける気候データは、主に史学者の手によって完成している)地理的にも、モンスーンという紐帯で華南辺りまでカバーしうるデータベースである。続く2022/03/07
アメヲトコ
10
22年3月刊。著者は理学博士でバリバリの理系。前半は年輪酸素同位体比にもとづく古気候復元の理論的解説で、その解像度の高さに驚かされます。後半は歴史的な気候変動と社会との関係の分析で、本書の特長はそれを「適応」という視点から読む点にあります。数年ごとの短期変動・数百年ごとの長期変動よりも数十年ごとの中期変動こそが人間社会へのインパクトが大きいといい、とくに良好な気候が長く続いたときこそが人間側がそれに過適応してしまい、そこが危機につながるとの指摘は色々と身につまされるところがあります。2022/03/17
どら猫さとっち
9
歴史は気候適応によって作られる。古気候復元の最新データに基づき、史資料と照合、地球環境問題に気候適応史研究の必要性を説いた、画期的な一冊。自然と人間の関わり、それは歴史においても、最も重要な要素である。幾多の危機を乗り越え、知恵を出し生かした気候適応。今大事なのは、気候適応からの生きる知恵ではないだろうか。2022/08/20
ノルノル
6
著者は1963年生まれの京大理学部→院が名古屋大で理学博士の現在名古屋大学の環境学の教授。専門の古気候学で、画期的な樹木年輪セルロース酸素同位体比法を開発・駆使し、それまで成しえなかった過去数千年の気候を年単位でシームレスに復元することに成功した。本書はその成果を主に日本史研究者や読者層へわかりやすく説明したもの。サンプルの中部以西2500年の気候復元データを駆使した長周期、中周期、短周期変動の分析、そして中周期変動が従来の研究の盲点、かつここが日本列島の人びとに深刻な変化を強いてきたことがわかる。+2022/02/25
-

- 電子書籍
- 精神分析入門(下) 新潮文庫
-

- 和書
- ことばの魔術師井上ひさし