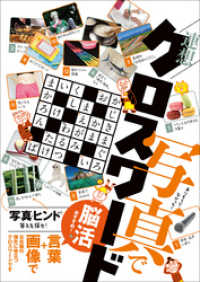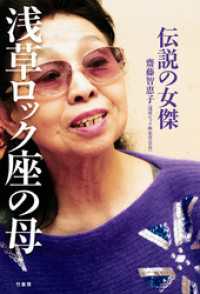内容説明
東日本大震災の津波の被害状況を調査したとき、不思議なことに気づかされます。
津波が到達した「浸水線」をたどっていくと、なぜか神社が現れるのです。一度や二度ではありません。神社のすぐ前まで波がひたひたと押し寄せた、そういう場所がやたらに多い。また、撮影された津波の映像も神社の境内からのものが少なくない。いったいこれは偶然なのでしょうか……。
たとえば福島県の沿岸部、新地町から相馬市、南相馬市までの神社84社をすべて訪れ、地図に落としてみると、多くの神社がきれいに浸水線の上に並ぶではありませんか。高すぎもせず、また津波に呑みこまれることもないギリギリの場所に、まるで津波を止めたかのように神社は建っていたのです。むろん被災した神社もあります。しかし、そこを訪れると、瓦礫のなかに石碑が残っており、神社が近世に移転してきたという来歴が記されていました。
われわれの先祖たちは、古来、地震、津波、台風など自然災害と向き合って生きてきました。そして、その教訓を、神社、地名などさまざまな形で伝えようとしてくれた。本書ではそうした数々の時を超えたメッセージに耳を傾け、明日への指針をさぐります。
目次
第一章
神社の手前で津波が止まった?
第二章
歴史津波の痕跡をたどる
第三章
神社に残る津波の“記憶”
第四章
傾聴すべき災害のメッセージ
第五章
警告は無視された
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
N.Y.
3
間違いなく神社は警告してた(してる)2015/04/25
りゅうごん
2
東日本大震災の後、津波を免れた共通点が神社だった。 そのことに気づいた筆者たちは、被災地にある神社をめぐり、そのルーツをたどる。すると、日本の歴史の教科書には詳細は掛かれていない大地震が大昔に何度も起こっていた。歴史では誰がどうしたということはたくさん書かれているが、自然災害に関する記述は少ない。というか生き残っていない。数少ない現地の言い伝えや石碑にそれが残っている。 色んな要素があって日本の歴史があるのだと感じた。2022/06/30
緑のたぬき
2
東日本大震災時に神社が津波到達の境界線だったことについての取材記録。津波石碑、江戸街道なども貞観津波被害から、高台に位置するため、今回の津波被害は少なかった。科学より自然を克服出来るどと錯覚し、明治以降に低地まで開発したエリアの被害が大きかった。これは伊勢湾台風の干拓地被害とおなじ。我々は先人と歴史にもう少し学ばないといけない。2020/06/18
かねかね
2
神社は避難場所でもあるんですね。地名の書き換えの話が興味深かったです。2017/05/05
コカブ
1
福島県で調査・測量の仕事に携わっていた熊谷氏が、東日本大震災の後に津波で神社が助かった例が多い事に気付き、それを元に以前の勤め先の高世氏に相談して、これを深めたドキュメンタリーを制作した。それを本にしたのが本書だった。神社が助かった理由は不明だが、東北地方では貞観津波・慶長津波の経験がある。そのため、津波の被害を受けない地域に集落が作られた事が理由ではないかと推測する。また、神社は標高の高い場所に作られる傾向があるので、これも一因となったようだ。思わぬ場所に歴史が眠っているのだと気付かされた。2013/09/15