内容説明
平安貴族の住宅様式である寝殿造。複数の建物配置が寝殿を中心に左右対称であるのが特徴とされながら、建物は現存せず実像は謎につつまれている。はたして寝殿造とは何か、その本質はどこにあるのか。遺構や絵巻、史料から貴族の住宅を通覧し、寝殿造の通説を徹底検証。院政期における建物・空間の変容を探り、これまでの住宅史に一石を投じる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
86
平安期の貴族は左右対称の寝殿造りの邸宅に住んでいたとされるが、その言葉も江戸時代に生まれたもので現存する建物は皆無だとは。各地の復元模型や再現施設も遺構や史料に基づくとされるが、その史料自体が信頼性の低い想像による幻想でしかないと言われたら何を信じていいのかわからなくなる。私たちが当たり前と思っていた歴史上の通説や常識はどんどん変化しており、その最新の変化を伝統と崇めてきたのは建築史だけでなく皇位の女系継承に関する議論も同じだ。信仰や崇拝は盲目になるのと同義であり、常に複眼と疑問の心を持たねばと痛感する。2022/01/17
びっぐすとん
20
図書館本。教科書で習った寝殿造は平安時代のみではなく江戸時代まで続く公家の住宅スタイルであること、しかしながら教科書で習うような左右対称の形式とは幾度の戦乱や大火で消失し、現存するものがないので実証出来ないらしい。僅かに寺社に形式を窺える。住宅といっても敷地面積がとんでもなく大きいので、庶民には屋敷の大きさも想像が難しい。現在の寺社でもわかるが、柱ばかりで壁がなく障子で外気を遮り、間仕切壁、天井がない部屋は寒かっただろう。蔀や御簾、几帳、屏風では寒さもプライバシーも遮れない。構造がシンプルとはいえ、火事→2022/01/28
アメヲトコ
10
21年4月刊。日本住宅史における寝殿造の位置付けを再考する一冊。寝殿造の本質はどこにあるのかをさまざまな史料を駆使して検討し、また「寝殿造から書院造へ」という単線的な図式を否定し、むしろ両者が並存しつつ変容していく過程として描くなど、興味深い指摘の多い内容です。2021/07/11
田中峰和
6
寝殿造は平安貴族の邸宅として知られる。壁がなく、柱だけで構成されている建築物は、夏の暑さ対策として有効だったが、冬の寒さに耐えられたのだろうか。十二単のような重ね着が寒さ対策だったという説もある。我々は大河ドラマなどで再現される寝殿造に影響を受けてしまう。平安時代から院政期に移る中で寝殿造も変遷してきた。その後、室町時代の武士の台頭によって、書院造が広まってくる。寝殿造から書院造へ。貴族とは違う生活様式をもつ武士たちは、新たな建築様式を生み出してきたのだ。2025/02/15
ゆの字
5
ひと口に寝殿造と言っても、漠然としたイメージしかなくて、それこそ「寝殿造鳥観図」が刷り込まれていた。それがまあ、想像力を駆使した産物だったとは恐るべし。図版が多く示されているのも良かったし、院政期以降の寝殿造の変容が理解できたのも良かった。時々目が滑りながらも読み終えると、最後に掲載されている江戸時代の九条家本宅の屋敷図を見て、寝殿造の名残があると認識できるくらいには理解が深まっていた。図書館本だけど、自分でも購入しようと思う。2021/04/17
-
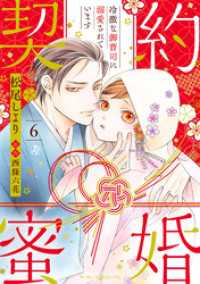
- 電子書籍
- 契約蜜婚~冷徹な御曹司に溺愛されていま…
-

- 電子書籍
- 十九歳の純潔【分冊】 5巻 ハーレクイ…
-

- 電子書籍
- とある魔術の禁書目録 外典書庫(2) …
-
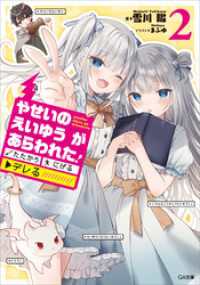
- 電子書籍
- やせいのえいゆう が あらわれた! た…





