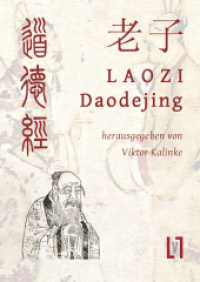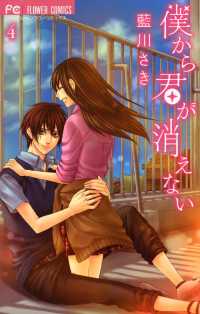内容説明
ジョージ・オーウェル賞受賞作品
権威主義体制下の「プーチン時代」において、ロシア人は個人の志と国家や社会の要求という、二つの大きな圧力の間で「板ばさみ」に苛まれながらも、何が有利になるのか、「狡知」をはたらかせて生きている。本書は、抑圧下の現代ロシアを舞台に、主に7人の群像が活写される。
「プーチン政治の映像プロデューサー」とされる国営テレビ局の最高責任者から、チェチェン戦争の凄惨な現実を目の当たりにした人権活動家、尊敬を集めた聖職者で、教会を厳しく批判した神父、クリミアで親ロシア派として住民投票し、夢と現実の間で悩む実業家、ソ連強制収容所での流刑を経て、人権団体「メモリアル」の創設に参加した活動家、プーチン政権と歩調を合わせて慈善活動する医師、国家資金横領で自宅軟禁処分を受けた演劇界きっての演出家、開放的で野心もあるが、今ある安定を望む「プーチン世代」の普通の若者たちまで、多種多様なロシア人の軌跡を追い、その集団的な潜在意識を探る。
『ニューヨーカー』モスクワ特派員が、体制派から反体制派まで、各世代、各立場の人々に密着取材、プーチン支配下での葛藤と妥協、したたかな「ずる賢い人間」の心奥に迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ばんだねいっぺい
33
ディストピアとしてのロシアがメディアや宗教、チェチェン、クリミア等の枠ごとに語られていく。そのどこにも板挟みの状況がある。ウクライナ戦争のなぜを求めて読書したが、似たようなことは、どこの国にもあると思った。ずる賢いことが、全体から見て、真に賢いことかと問うこと自体が難しい場合もある。2024/04/10
ふな
8
ウクライナ戦争をきっかけにロシア情勢を知りたくなり購入。恥ずかしながらクリミア併合のことは全く知らなかった。ロシアではどんな職業であっても自分のやりたいことを貫くには国家との連携が不可欠で、そこから外れると制裁を受ける羽目になる。国家に利用されつつもしたたかに立ち回る女性人権活動家のお話が印象に残った。翻訳の読みにくさもあってなかなか進められなかったが、読んでよかった。2025/07/07
harumi
6
雑誌『ニューヨーカー』のモスクワ特派員である筆者が今のロシアに生きる様々な立場の人たちを取材しまとめた本。ロシアの人々が今のロシアの状況を一体どう思っているのかを知りたい人にはうってつけの読み物。そこにはプーチンを支持するしないなどという優雅な余裕などなく、「国家の圧力に押し潰されそうになりながらも自分にとり何が一番得になるかをしたたかに計算し」つつ、必死にわずかに残っている自由を守ってい生きている姿がある。それがロシアの「ずる賢い人間」なのだ。西側に暮らす私達と比べると生きることははるかに難しい。2024/04/01
sakadonohito
4
あまり頭に入ってこなかった。。ロシアで生きる人々がどうプーチン政権下であがいて生きているかを書いている。テレビ関係、聖職者、チェチェン人、クリミアで生きる人、ドンバス地域で医療活動をする人、バレエダンサーなどなど。圧力があり自由には生きられない世界でどう生きていくか。生きるために主義主張を捻じ曲げることを強制される。大変ですね。2025/06/26
takao
3
ふむ2024/04/22