内容説明
著者はアーティストとして、全国各地や海外で現代アートの活動をしてきた。
しかし、3.11の震災後に自身の活動への違和感を無視できなくなってきた頃、友人のジャーナリストに「マタギと飲もう」と誘われ新潟県村上市山熊田、マタギの集落に赴く。
そこでは電気がなくても生きていけるような、たくましい暮らしがあった。
自分たちが弱い存在であり、手を抜いたら命を落とすような世界にいることを自覚しているがゆえの強さ。
田舎暮らしという言葉が発する牧歌的なにおいはそこには皆無だ。
カタカナ皆無でよくわからない言葉、山から切り出した薪で煮炊きし、伝統的な狩猟をし、スケールでかく酒を飲む。
水も薬も美味いご馳走も燃料も、工芸素材や心奪われる絶景までも、全て山にある。
体力たくましい爺や婆がいる。しかもハイセンス。皆オシャレだし心も豊か。
東京にいては想像もつかないような世界がひろがっていた。
山熊田に移住して、マタギ頭の家に嫁いだ著者が本書で訴えたいのは「消費社会にはない選択肢がここにはある」ということ。
山熊田では四季というサイクルのなかで同じことが繰り返されている。
それこそ人間本来の生き方ではないか、と著者は問う。
令和の傑作移住日記の誕生です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ワッピー
39
現代アート作家が縁あって、樹皮から作る古代布・羽越しな布の保存に関わり、マタギ生活の残る山熊田村に移住した生活誌。マタギの嫁になった経緯はさらっと流されているが、伝統的な生活形式、焼き畑と狩猟生活で得られる四季折々の山の幸の豊かさとともに、また断熱性の低い住居や高齢化による限界集落化、そして虫との壮絶な戦いも描かれている。古代布を作る工程の大変さもさることながら、熊汁を作るにしても多くの材料とまわりの助けが不可欠な共同体の暮らしの良さと大変さがわかります。香り高い野生のマイタケに憧れ。山好きにおススメ!2025/01/31
to boy
23
これはなかなか面白い一冊。日本三大原始布の一つ羽越しな布の貴重な継承者となった著者のなんとも痛快な人生。たまたま誘われたマタギとの飲み会を契機に新潟県最北部の寒村に嫁ぐ。18軒37人の小さな村。まるで明治時代に戻ったかのような暮らしと風習に戸惑いながらも前向きに受け入れていく姿勢が素晴らしい。山菜取り、薪割り、雪対策、そして頻繁に行われる男たちの宴会の支度。普通の人だったら逃げ出したくなるような生活を怪しげつつ楽しむ人柄が良かった。2024/04/12
tetsubun1000mg
18
現代アート作家として活動していた筆者がマタギとの飲み会に誘われて出かけた先が「山熊田」。 新潟県最北部にある村上市の山熊田という18軒37名の、いわゆる限界集落。 マタギが熊を狩り、日本三台古代布と言われる樹皮製の「羽越しな布」を作る人々が住む。 読みやすい文章で、次第に引き込まれていく。 山形新聞や長崎新聞に連載を持っているそうなので慣れているのだろうか。 マタギの生活や「しな布」の存在を知り織機を組み立てて織り方を習っていき再生の方法を探っていく過程がイキイキとして面白い。 出版はなるほどのヤマケイ。2024/04/30
niki
8
嫁になるまでの馴れ初めは一切なし。十八世帯しかない山奥の村で暮らすというのはどういうことなのか、偏見なく冷静に若い視点で楽しみながら暮らす筆者の筆致は正直で爽やかで笑える。冬に備えて準備する薪の量の写真は想像の遥か上、山菜や鮎や熊を獲り食するのだが、大雪で停電になり東北電力が衛生電話を貸してくれたエピソードが面白かった。文明が行政から支給されることが新鮮。特別原稿の機織りについて。村の人々は今までどれだけ搾取されてきたのだろうと悔しくなる。そこに諦めずに立ち向かった筆者は素晴らしい!2024/10/31
kaida6213
8
読みにくい箇所もあるが、現代美術から(もっと前野美術に触れるところから)マタギのシナ布にいきつくまでのストーリーは興味深かった。2024/06/29
-

- 電子書籍
- 闇金ウシジマくん【タテカラー】 ヤミ金…
-

- 電子書籍
- 【分冊版】昭和まぼろし 忘れがたきヤツ…
-
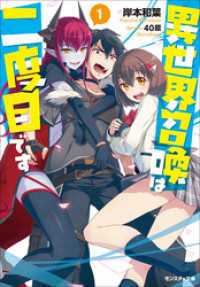
- 電子書籍
- 異世界召喚は二度目です : 1 モンス…
-
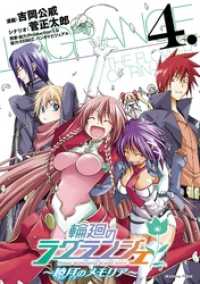
- 電子書籍
- 輪廻のラグランジェ~暁月のメモリア~ …





