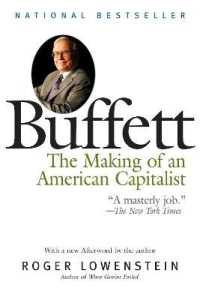内容説明
国内外で活躍するための必須スキルとされる「論理的思考」.だが実は,「何を論理的・説得的と感じるか」は普遍的なものでなく,ある国(文化)で論理的とされるものが,ほかでは非論理的だと受け取られることも.本書では,日や米とも異なるフランスの「論理的思考」と,それが社会的に構築される様相と背景を読み解く.
目次
序章
1 思考表現スタイルと論理的思考
2 学校の特別な役割
3 小論文の型と「論理的である」と感じる根拠
4 なぜフランスなのか
5 本書の構成
第一部 論文構造から生まれる論理と思考法――哲学と文学のディセルタシオン
第1章 論文の構造と論理の型――エッセイとディセルタシオン
1 「論理的」であることの探求
2 ディセルタシオンの構造と論理――エッセイとの比較から
3 構造から導かれる米仏の論理の特徴
第2章 哲学のディセルタシオンと哲学教育――吟味し否定する方法を教える
1 哲学のディセルタシオンの特別な地位
2 哲学教育の目的,内容構成と方法
3 哲学のディセルタシオンを書く
4 哲学のディセルタシオンを分析する
5 小括――哲学のディセルタシオンに見る思考表現のスタイル
第3章 文学のディセルタシオンと文学教育――文学鑑賞と論理的思考
1 高校のフランス語(文学)教育――目的と構成
2 文学の論述問題
3 文学のディセルタシオンを書く
4 文学のディセルタシオンに見る弁証法の論理
第4章 ディセルタシオンの歴史――新しい社会の論理の模索,伝統と革新の接点
1 伝統的な教育――フランスの論理的文化と三つの形式主義
2 フランス革命とディセルタシオンの創造
3 哲学教育とディセルタシオン――自由に自律して考えるための訓練の創造
4 小括 ディセルタシオンは教育を刷新したか――変わったものと変わらなかったもの
第二部 論理的思考の段階的な訓練――ディセルタシオンを目指した言葉の教育の全体像
第5章 小学校で教えられる論理――言語の内的論理と視点の一貫性
1 文法・描写・物語を通した論理的思考
2 作文(r daction)――形式による論理的一貫性を学ぶ訓練
3 物語の創作における二つの訓練――視点による論理的一貫性と物語の「定義と型」の習得
第6章 中等教育で育まれる論理――「論証」から「弁証法」へ
1 中学校における「論証」――自然の配置から論理の配置へ
2 高校で育まれる論理――弁証法という思考の飛躍
3 小括――高校で育まれる論理と論理的思考
第三部 判断し行動するための論理――推論する,討論する,合意するための教育
第7章 歴史教育――過去の解釈と未来予想に見る推論の型,「合理性」の判断基準
1 フランスの歴史教育の構成――教科書に見る時間の概念と歴史認識
2 フランスの歴史教科書の構造と授業の構造
3 過去はどう語られるか――フランスの歴史授業の五つの特徴
4 視覚イメージで教える効果――見えるものから「見えないもの」を読み解く
5 いかに評価するか――良い説明(歴史の語り)と求められる能力
6 未来はどう捉えられているか――歴史教育に見る過去・現在・未来の構造
第8章 歴史教育の歴史に見る思考法の変遷
1 歴史教育の転換点(一九七〇年代の改革)――新教育とアナールの歴史研究の方法
2 揺り戻しと新たな発展――公民教育としての歴史と年代史・政治史の復活(一九八〇年代)
3 史料から構築する歴史へ――生徒の多様化とデカルト的方法(一九九〇年代から)
4 グローバル化・情報化への対応――共通基礎の導入
5 二〇〇〇年以降のディセルタシオンの大衆化と歴史教育――理想と現実,断絶と継承,批判と実像
6 教育の大衆化とテーマとイメージによる歴史
第9章 市民性教育――合意形成の手続き
1 言葉の定義を通した合意形成と共通の文化の構築
2 学級の規則作り――手続きの遵守と形式主義(公民科)
3 言葉の定義から「判断の基準」を学ぶ
4 「社会は変えられる」――フランス革命の遺産を伝えるプロジェクト
5 哲学による前提の合意形成――歴史に学び,共同体の文化を形成する討論
6 討論から政治的行動へ
7 政治教育としての市民性教育――言葉の定義と手続き遵守の社会生活への適用
終 章 フランス社会の〈論理〉の構築――ディセルタシオンが導く思考表現スタイル
1 思考表現スタイル――思考・判断・表現の型
2 社会の利益か,個人の目的達成か――共和主義と民主主義
3 民主主義型の思考表現スタイル――補助線としてのアメリカ
4 結語 小論文の〈論理〉から考える社会の未来――フランス,アメリカ,そして日本
あとがき
参考文献
資料
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sayan
kan
yutaro sata
syuu0822
buuupuuu