内容説明
現代まで引き継がれる一元的支配――その原点は秦王政の「キングダム」にあった。
今の中国の一元的支配の根源は何か? 世界の今を解くカギは、すべて歴史の中にある――。誰もが一度は耳にしたことがある「歴史的事件」と、誰もが疑問を抱く一つの「問い」を軸に、各国史の第一人者が過去と現在をつないで未来を見通す新シリーズの第5弾! 初めて統一されて以降、二千年以上にわたって広大なエリアを保持し続けてきた「中国」。なぜいくたびも王朝交替を繰り返しながら、一元的支配体制は引き継がれてきたのか? 「辺境の蛮国」と見なされていた秦に現れた、希代の権力者の理想にその原点を見る。
【内容】
第1章 秦王政はいかにして中華統一を成し遂げたのか?
第2章 後進国の秦がなぜ最先端の社会体制を作り出せたのか?
第3章 始皇帝の理想は中華統一の達成であり、統一の維持ではなかった!?
第4章 その後の中国大陸で二千年にわたって影響を与えた「国家モデル」の完成へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
30
中国はなぜいくたびも王朝交替を繰り返しながら、一元的支配体制は引き継がれてきたのか? 辺境の蛮国と見なされていた秦に現れた、希代の権力者の理想にその原点を見る一冊。呂不韋の存在、戦国の七雄の関係の変化、六国平定と郡県制などに見る秦王政の中華統一から、他国出身者の登用などに見る後進国の秦がなぜ最先端の社会体制を作り出せたのか。統一に関する同時代へのインパクトや、その国家モデルがその後の王朝にもたらした影響に至るまで、わりとオーソドックスな内容でしたけど、その分コンパクトにまとまっていて読みやすかったですね。2024/04/02
さとうしん
12
伝世文献の記述を中心とした比較的オーソドックスというか教科書的な作りの本。「古典中国」を押し出してる所がこの著者らしいといったところか。これは著者というより「世界史のリテラシー」シリーズ全体のコンセプトでもあるかもしれないが…… 目新しさはないが、特に間違ったことを書いてあるわけでもないので、手堅い内容を求める向きには悪くない本だと思う。2024/02/10
ジュンジュン
11
中国の枠組みが整う過程を、始皇帝を中心に後漢まで視野に入れて描く。2200年前に生まれたシステムが現在も生きている事に改めて驚く。その背景には国教となった儒教による共通認識があったと思うがどうだろう?2024/11/05
金監禾重
5
140ページ程度の薄い本だが、氏族制解体と法家思想に注目して始皇帝の帝国の興亡がわかりやすく書かれている。他国の人材を重用して君主権力を強めた秦は他国を圧倒して拡大する。しかし新支配地ではなかなか氏族制のしがらみを克服できなかったことが、出土木簡や前漢初期の郡県制地域・封建制地域を塗分けた地図に現れる。前漢は郡県制と封建制、皇帝と天子という、秦の厳しさと周の緩さのいいとこどりによって「漢字」「漢民族」というように後世までシナを象徴する帝国を築いたという印象。2025/07/16
えふのらん
3
宗族による礼政一致に儒家、秦の法治主義に法家を見出して中国の統一を思想的交代劇と読んでいるのが渡邉さんという感じ。商鞅による分異の制の施行と氏族性の解体、什伍の制による相互管理社会の形成、果ては血縁に左右されない勲功(軍功爵)までが反儒教政策の一点で結びつく。(韓非子は韓非子で墨家を攻撃していたらしい)儒教が幅を利かせない世界とは思想がぶつかり合う無法地帯=諸子百家ということなのかもしれない。中国というと礼治主義や科挙を思い出すが、そういった諸所の制度が形成される段階を手際よくまとめてある。2025/04/23
-

- 電子書籍
- #ふりむかないで#ふりむいて【単話版】…
-
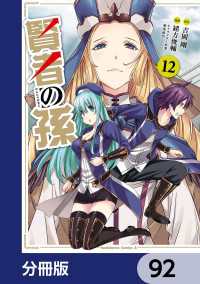
- 電子書籍
- 賢者の孫【分冊版】 92 角川コミック…
-

- 電子書籍
- お見合い相手はうちのボス【タテヨミ】第…
-
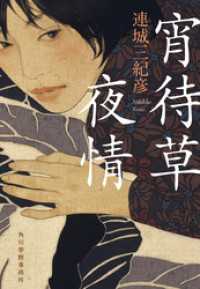
- 電子書籍
- 宵待草夜情 ハルキ文庫
-
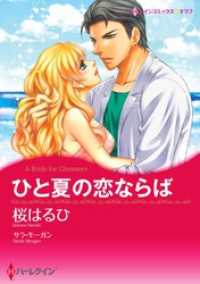
- 電子書籍
- ひと夏の恋ならば〈【スピンオフ】グレン…




