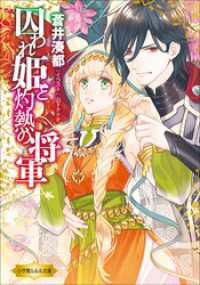内容説明
帝国陸海軍の作戦行動の指揮・決定権限である統帥権。天皇大権に属し、その「独立」は内閣からの干渉を阻止した。そのため満洲事変以降、陸軍の暴走をもたらした最大の要因とされてきた。しかし近年、通説の見直しが進む。明治政府はなぜ「独立」を必要としたのか。否定論者がいながら、なぜ「独立」は維持されたのか。海軍の役割とは。本書は、軍事の特殊専門意識に着目、明治からアジア・太平洋戦争敗北までの通史を描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
123
過去に正しいと思われた法や制度が、後の世を混乱させた最たる例か。維新後の軍事指導の混乱を痛感した明治政府は、非政治的な専門家集団たる軍を作るため統帥権独立と軍部大臣現役武官制を決めた。しかし戦争が実力行使による政治の一形態であるなら、両者の分離には最初から無理があった。そこに「素人の政治家は軍事に口を出すな」という軍人のエリート意識が生まれ、現地部隊や中堅将校の暴走で統制が崩壊した軍が勝手に動く口実に統帥権が悪用されるに至ったのだ。明確な決定権者を決めなかった日本政治の根本的欠陥が、諸悪の根源といえよう。2024/05/08
skunk_c
77
海軍と政治に関する本を上梓していた著者だが、本書はその研究を見事に昇華している。表題に関して明治期から丹念にその意味を位置づけ、昭和期の混乱がなぜ起こったかを明らかにしている。統帥権の独立とは何かという本質的な問題について、明治期の法規から丁寧に論じていく。また、政治過程についても、個人の個性に引きずられることなく、テーマにきちんと位置づけながら論じている。「おわりに」はその見事な要約となっているので、そこから読むのがいいかも。実は本書を手にして高杉氏の本と並行して読んだのだが、その次元の差は大きい。2024/07/24
kk
22
図書館本。統帥権独立にまつわる問題を、自律志向が極めて高いエキスパート集団を如何に管理し、国家社会全体の利益の中に位置付け得るかという問題として捉える。その上で、明治建軍以来の歩みの中、「軍事の特殊専門意識」が旧憲法下の分立的統治構造によって助長され、さらに部内統制の失調や管掌範囲に関する敏感性などと相俟って、政治優先原則に失敗したとする論調。単なる軍部の横暴や統治構造上の失敗と捉えるのではなく、専門性に対する過度の尊重に弊害の所在を見るという、ある意味で日本社会論的とも言える視点。勉強になります。2024/06/05
ジュンジュン
15
本来、軍が政に関与させない(逆も然り)為だった統帥権の独立が、30年代、軍部の暴走を招き、日本は敗北へと至ったのは何故か?著者は軍の暴走は統帥権の独立に起因するのではなく、軍内部の統制欠如が原因であり、本来別件であった二つが混ざり合い複雑化したとする。統帥権の独立を支えたものは、軍事の事は軍人にしか担えないという「特殊専門意識」だという。この考えが広く認識されていた為、敗戦まで存続したというが…難しかったなあ(苦笑)。2024/04/12
MUNEKAZ
14
「統帥権の独立」問題を理解するには優れた内容ではないか。類書だと陸軍ばかり注目されるが、本書では海軍にもしっかり言及しているのが良い。「政治」と「軍事」の優先権が付けられず、軍部と政府が対等の関係で各々の管轄権の争いを繰り広げ、大局的な見地ではなく手続き論で紛糾していく様がよくまとめてある。また明治憲法の持つ分権的な性格故、軍部のみならず例えば文官の外務省も自らの専門事項に絡む事柄には反発するなどの事例も興味深い。専門家集団をいかに統御し、セクショナリズムを防ぐかという今も考えなければならない課題である。2025/05/04