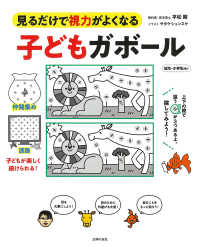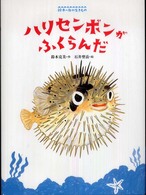内容説明
フリートーク、エピソードトーク、掴みに切り口、語り口……数多の才能を見出し、「オードリーのオールナイトニッポン」等でトークの壁打ち役を務める放送作家が、ついにその術を皆伝!!
オードリー 若林正恭さん推薦!!
「この教室の授業のせいで、痛い目にあった時に
「儲けた~」と思ってしまう身体になりました。」
フリートーク、エピソードトーク、掴みに切り口、語り口……本書は、数多の新人アイドル、芸人に寄り添い、巧みなアドバイスで彼らのトーク力に磨きをかけてきたメンター、放送作家・藤井青銅氏がそのトーク術についてまとめた一冊です。
「トークの途中がおもしろければ、オチは無くてもいい」
「誰かに聞いてもらうことで、話し方のコツを見つけた人は伸びる」
「〈心の動き〉を切り口にすれば、トークの題材には困らない」
「キャラを作ったり、背伸びしたり、パブリックイメージになんて、合わせなくていい」…etc.
若林正恭さん、山里亮太さんを描いたドラマ『だが、情熱はある』(日本テレビ系)へ本人役での出演も記憶に新しいところですが、YouTubeチャンネル「オードリー若林の東京ドームへの道」では、第一回ゲストとして若林さんと“二人っきりサシ対談”。
番組を観た視聴者からの「?銅さんのトーク本があったら、絶対に読みたい!」という多くのリクエストに応え、本書の執筆がスタートしました。
「あの人は、どうしていつも面白いネタを持っているのか?」
「つい聞き入ってしまうトークには、どんな秘密があるのか?」
“面白いトーク”とは何か?を突き詰め、話し手のボールを真摯に受け取り、返す、その運動を40年以上も続けるなかで導き出したトーク術を整理し、アップデートさせながら執筆された本書で、自分に合ったトークの正解が、きっと見つかるはずです。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホッパー
Kanonlicht
yutaro sata
タルシル📖ヨムノスキー
すいへい