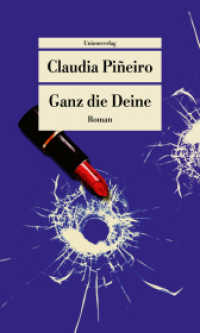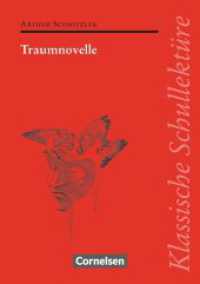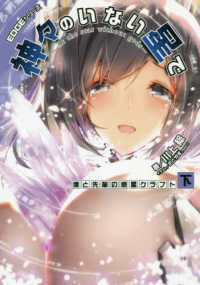- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
分断が深まる世界。複数の〈正しさ〉が衝突するなかで、人は難題を前に「何でもあり」の相対主義に陥りがちだ。人生の切実な「問い」に直面して 筋を通す ための倫理とは? カントに代表される義務倫理、ミルやベンサムが提唱した功利主義に対し、アリストテレスを始祖とする徳倫理はこれまで充分に注目されてこなかった。近代が置き去りにした人間本性の考察と、「思慮」の力に立ち戻る新たな倫理学の潮流が、現代の究極の課題に立ち向かう!
◆積極的安楽死は認められるか?
◆妊娠中絶の自由か胎児の生存権か?
◆テロリストの逮捕か人質の命か?
◆安全基準か雇用の最大化か?
【徳倫理とは】
アリストテレスを始祖とし、人間本性の考察に基づいて思慮の力と「どうしたいか」を重視する倫理学。カントに代表され「すべき(でない)」と人を縛る義務倫理、ミルやベンサムが提唱し、経済学と結びついた功利主義と異なる第三の潮流である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
175
事例豊富。題の「つなわたり」とは、普遍的な倫理の独断論と極端な相対主義の間を行くという意味で、そこから心のあり方(徳倫理)を見直す試みである。その際、徳だけでは行為と結びつかないから、アリストテレスが中庸という概念で示唆したように、両者を繋ぐ〝思慮〟の吟味を必要とする。そこで、マッキンタイア、ヌスバウム、マクダウェル、フット、ハーストハウス、イグナティエフらの議論を参照しつつ切り込んでいく。明快な答は出ないにせよ、この試みは無駄に思えない。迷いに向き合う柔軟な思考そのものに倫理の力が宿っているようだった。2024/05/18
ふみあき
41
なんだか得体の知れない書名だが、要は(カントの義務論、ベンサムの功利主義と並ぶ倫理学の潮流で、アリストテレスを始原とする)徳倫理学の入門書。いや、入門書と言うほど易しい内容ではないか。正直、徳倫理学について、フロネーシス(思慮)に基づく個別実践的なスタンスだということ以外、その全体像について、よく理解できたとは言えない。が、安楽死だったり癌告知だったり、後進国での(先進国とは基準の異なる)臨床試験の話だったり、紹介されるアポリアの数々を経巡るうち、自分の先入観を打ち砕かれることも度々であった。2024/03/01
buuupuuu
18
徳倫理学の入門書。ヌスバウムとマッキンタイアを現代的な徳倫理学として、互いに補い合うものとして紹介している。徳倫理学は、原理ではなく、熟達者の判断という概念に訴える。思慮や中庸といったものはその内実を明確化できないことが弱みであるように見える。しかしこれは、倫理的状況というものの性質に由来するものだと言えるのではないか。私達は現実の状況に理想をそのまま当てはめることはまず出来ないが、かと言って開き直って現状追認に走ってしまうべきでもない。思慮というのは難しい状況の中で舵取りをすることなのだと言えそうだ。2024/03/02
おやぶたんぐ
6
装丁も題名もカジュアルだけど、中身は結構骨太。安楽死や妊娠中絶、癌告知等々の難問に対し、“あるべき姿”を求める義務論的アプローチでも、結果を追い求める状況主義(功利主義)的アプローチでもなく、生を実証する可能性ー“潜在力”アプローチで臨もうとしているらしい。決して明快ではないけれど、安易に流れることのない“思慮”を重んじる徳倫理の上記アプローチは魅力的だと思う。2024/04/13
ちくわ
5
ざっくりとした議論がなされているのかと思って手に取ったが中々骨太な議論が展開されており、動物の倫理のあたりは理解できたかは怪しい部分がある。本書自体は、いわゆる徳倫理学をベースとした記載になっており、アリストテレスにはじまり、現代のヌスバウムの議論に至るまで、多種多様な議論が展開されている。いわゆる義務論や功利主義と比較して、個人的には善い生き方を志向する観点では馴染みやすい者であり、しっくりくるところである。ただ、実践知を重要視する思考であるからか、ある程度の覚悟が必要な思考だとは感じる。2024/05/01