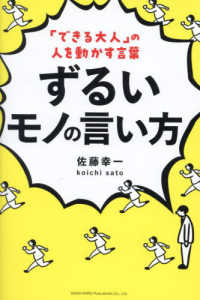内容説明
主体と存在、そして所有。著者の重ねる省察は、われわれを西欧近代的思惟が形成してきた「鉄のトライアングル」の拘束から解き放つ!
「ほかならぬこのわたし」がその身体を労して獲得したものなのだから「これはわたしのものだ」。まことにもっともな話に思われる。しかし、そこには眼には見えない飛躍があるのではないか……? ロックほか西欧近代の哲学者らによる《所有》の基礎づけの試みから始め、譲渡の可能性が譲渡不可能なものを生みだすというヘーゲルのアクロバティックな議論までを著者は綿密に検討する。そこで少なくともあきらかにできたのは、「所有権(プロパティ)」が市民一人ひとりの自由を擁護し、防禦する最終的な概念として機能しつつも、しかしその概念を過剰適用すれば逆にそうした個人の自由を損ない、破壊しもするということ。そのかぎりで「所有権」はわたしたちにとって「危うい防具」だという根源的な事実である。主体と存在、そして所有。著者の重ねる省察は、われわれを西欧近代的思惟が形成してきた「鉄のトライアングル」の拘束から解き放ち、未来における「手放す自由、分ける責任」を展望する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tokko
12
近代の西洋哲学における「所有論」から掘り起こして、「所有(権)」の過剰なまでの主張・行使が見られる現代の新自由主義の世界で、再度「所有」とは何なのかを鷲田さんが問いなおす。もちろん「自由」や「権利」といった近代思想の産物とともに、「所有」も必然的に生まれた概念であるという歴史的背景がありますが、他者を疎外するための「所有(権)」ではなく、「共」へと引き継いでいく義務としての「所有」、託された「物」としての「所有」という視点が提案されている点が興味深い。2024/05/28
Kai Kajitani
10
歴史的な慣習として多様な成り立ちをしてきた「所有」は、近代以降社会の根幹をなす普遍的な権利として、あらゆるところにその影響を及ぼしてきた。その結果人びとの生活を守る盾であるはずの「所有権」が、社会の「よき習い」を破壊するという矛盾がうまれる。本書はこうした近代的所有権を相対化するヒントとして「所有は、それを放棄することによってはじめて可能になる」というヘーゲルの議論に注目する。そして、あるものを誰かから「受託」し「適切に保つ」ことをそのオルタナティブとして提唱する。所有の奴隷にならないための優れた指南書。2024/03/17
たか
6
所有をめぐるロックやヘーゲルを始めとした多様な論者による議論を参照し、現代の所有権のあり方に新しい見方を与える。所有権は自由を支える重要な概念だが、行き過ぎると「所有が主人になって、所有者が奴隷になる」。自らの所有物を「どう扱おうとわたしの自由である」という自由処分権の主張を疑問視し、託されたもの、いわば「当主」としての責任を引き受けているという考え方へとひらく。ひとがもつ才能や知識についても同じ事が言える、という洞察にはなるほど。資本主義やリバタリアニズムを考えるうえで重要な視点を貰えた気がする。2025/04/29
YASU
4
立岩が私的(個人的)能力―生産―所有の関係を論じたのに対し、本書はロックに始まる哲学的論考を丁寧に読み解き、根源的に所有を論じている。資本の本源的蓄積、とくにイギリスの囲い込み運動が私的所有権の法的確立を要請したのは既知の事実だが、著者はさらに近代個人的自由(所有権)と、コモン的共同体的受託とを対比させることで、所有の受責性まで俎上に乗せる。アーレントからグレーバーまで引きながらの行論はさすが説得的。こういう方向からの、能力主義批判もまたありえましたよ、立岩先生。否、とっくにご存じだったかな。2025/06/06
水
1
鷲田清一はエッセイや軽めの評論本で愛読しており、本気の思想書に挑むのは初。これまでの読みやすさがいかに配慮されたものであったか分かった。全体をとおすと1−2割程度しか理解できていないように思うが、最終章にちかづくにつれ分かりやすく整頓されてゆく。乱暴にまとめると、ほんらい「所有」とされているものを的確に捉えるためには「受託」と言い換えるべきであって、そこには処分権はふくまれず、むしろ「後世へと引き継ぐ」という姿勢が求められているのだ。個の便益だけでなく共への意識を前提としなくてはならない。2025/05/28
-

- 電子書籍
- 宇崎ちゃんは遊びたい!【分冊版】 6 …