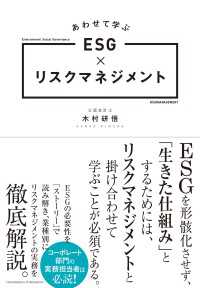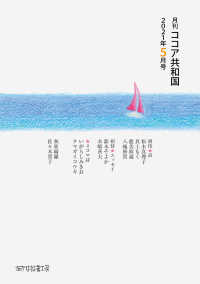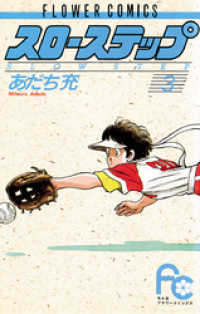内容説明
国宝,重要文化財はもちろん,身近な文化財も私たちの生活にきわめて重要な意味を持つ.容易に失われてしまうそれらを,〈ものつくり文化〉とともに守り,つないでゆくには? 保存と活用とのあいだで揺れる文化財の過去と現在,未来と希望を,第一人者が語り尽くす.世界にも稀な文化財の宝庫日本を,真の「文化の国」へ.
目次
はじめに――水、空気、そして文化財
I 日本は文化財の国である
一 今、なぜ「文化財」なのか?
二 「文化財」の誕生
II 「文化財保護法」と日本文化
一 「文化財保護法」誕生まで
二 「文化財保護法」の歴史と未来
三 「災害頻発時代」の文化財――未来に向けた取り組みを
III 保存・継承、そして活用
一 保存と活用の矛盾を越える
二 価値を見きわめる――文化財保存科学の挑戦
三 「何も足さない、何も引かない」は可能か?――修理を深く考える
IV 「複製」は日本文化を支える
一 「複製」とは何か?
二 「複製」の可能性
三 追体験がひらく新たな文化の地平
V これからの日本文化のために
参考文献
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りぃ
4
近年の文化財保護法改正後に書かれた本が少ないので貴重だと思う(ただ、2021年改正の、無形文化財の登録制度のことが反映されていないかも?)。有形文化財にこだわりがあると書かれているとおり、無形文化財についての記述はあまりない。巻末に参考文献あり。2025/03/23
kokekko
4
良書。最初の方はおかたい「文化財」等の言葉の定義が続くが、5W1Hで語る記述する「物」の歴史、仏像やかけじくの修復の技術、コピー・レプリカ・フェイク、そして文化庁の予算がずっと少ないまま止まっている問題などわかりやすく記されている。文化財、美術品は『心のインフラ』という表現がとてもよかった。なくてもいいもの、なんて政治家には思わないで欲しい。大切なものだよ。2024/04/20
お抹茶
3
文化財に携わる人は読んでおくといいと思う。教科書ではなく,プロからの語り。1929年の国宝保存法によって国宝指定された物件の輸出は防げたが,この段階では文化財という概念はなく,建造物や美術工芸品といった個別の扱いだった。1950年に文化財保護法が成立して,包括的に扱われるようになった。災害大国日本で,指定文化財以外の文化財を災害時に救うべきかという問題は悩ましい。保存に重点を置かれていた文化財に対し,金銭的効果を生み出す手段として「活用」という社会的ニーズにも応える必要がある。2024/03/05
バッシー
3
文化財は「日本人の心のインフラ」とはなるほどと思った。一度失えば、二度と戻らないもの。昨今の我が国の状況を考えると、暗澹たる気持ちになってくる。2024/01/28
takao
2
ふむ2024/05/15