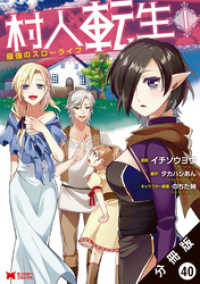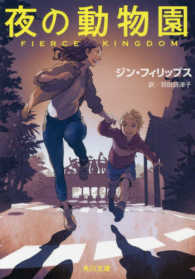内容説明
遠い過去の時代に、人間はどのような心を持ち、なにを考えていたのか。それを知るには、まだそれが残っている現場に身を置くことだ。若き人類学者・中沢新一は秘教の地へと向かう。恩師ケツン先生から得た知恵は、やがて独自の思想の構築へとつながり、「精神そのもの」へと導いていく――人生を賭けた冒険の書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
50
独自の道を探り辿る。理解など到底叶わないけど、我輩なりに…2024/04/12
やいっち
12
著者は、「いまから四十数年前、私は一人でネパールにでかけて、その地でひっそりと難民の暮らしを送っていたチベット人のラマ(先生)のもとで、「ゾクチェン」という古代から秘密裡に伝えられてきた精神の教えを学び始めた。この本で私は当時の記録と記憶をたよりにその修練の過程をできるだけ詳しく再現しようと試みた」というまさに四十数年の修練の集大成の書。2024/04/12
メガネねこ
3
★★★★★私は中沢新一を通してチベット仏教を知り、ネパールやチベットにまで赴きダライラマにまで会いに行った。本書はチベットのモーツァルトと並べて、チベット仏教の哲学・奥義を知るには最も最適な導入本だと思う。昔は難解な文調だった中沢新一の解説も彼も歳を得て随分易しくなった。精神哲学を学ぶ為の必読書。2024/12/21
Kadwaky悠
3
「チベットのモーツァルト」を確か18か19歳に初めて読んで衝撃を受けて、価値転倒を起こして人生の軸足を変えてしまったぼくには、本著はすごく心地の良い一冊となった。吉本隆明の「アフリカ的段階」もまた読み直したい。ふと「虹の階梯」をぼくは読んだのだろうかと思ったが、いま手元にないので「レンマ学」を読み始めた。こちらは学術的なので最初は読み進めるのに難があって止めてたのだが、本著を読んでから理解が早くなった気がする。2024/07/10
yo_c1973111
3
洞窟壁画の時代の次は「象徴革命」とあらわすことができるとのこと。農業革命や文字の発明は人類の象徴的思想、精神的発展によるという指摘に冒頭からふむふむとなりました。本編ではヨーガや加行の方法などの伝承方法こそが象徴的に感じられました。パドマサンバヴァによってチベット各地に埋められた教えの数々をテルトンという修行者によって発掘され、あらたに神話的制作によって再解釈されて伝わってゆくということらしい。つまり文書が固定物として伝承されるのではなく、時代に揺すられながら常に再解釈され続けて伝承されるということです。2024/06/23