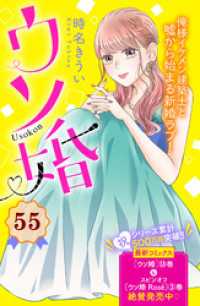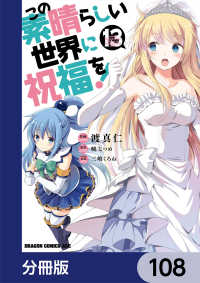内容説明
日本における供犠は、「食べる文化」である――。動物を「神への捧げもの」とする西洋の供犠との対比から、日本の供養の文化を論じ、殺生・肉食の禁止と宗教との関わりに新たな光を当てた名著が文庫化。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひさしぶり
21
民俗・信仰・祭祀や日本書紀等や絵巻から日本の自然観や動物観を見つめる。稲作文化が定着し徴税が稲中心となった(贄→嘗)が律令制の中には調や租がある。白(コメ)は清浄で血は穢れという思考は仏教の不殺生という考え方以前の日本の伝統的な「忌み」の感覚では。神饌のおさがりを共に食すという行為は神に捧げられた特別な食材を食べると文字通り神と同質の身体をもつようになると考えられたのでは。専門的で素人が手にとるべき本とは言い難いけど刺激的でした。 2023/09/06
∃.狂茶党
16
柳田民俗学以降横道にそれた、祭祀と供犠の関係の洗い出しをおこない、 共に食す、という日本人の原像的祭儀に光を当てる。 日本の供養文化は、職業的やましさと強く結びついている。 一見仏教的なものに見えるが、牧畜を行わなかった日本での、自然の恵みといった概念が生み出した神意識と、大陸より導いた国家システム、仏教や道教の世界観が渾然となって生じたものである。 祭祀は、経済活動なのではないか? 日本的な生贄や人身御供などの基本図書。 象徴を読み解く時に、文化圏の違いを意識する必要を強く感じさせる。2022/07/25
わ!
6
供犠(くぎ)、つまりは「イケニヘ」の話で、日本に供犠があったかどうかの話から始まり、八幡宮などにみる「放生」の話へ、そして供養の話へとスライドして行く。かなり丁寧な話となっている。そして(とはいえ、ページ数からすると全体の1/5程度だが)最後の第三章で「人身御供」へ、そしてなんと、あの柳田國男翁の一目小僧の話へとつながってゆく。この柳田翁の一目小僧論をここまで掘り下げた話は初めて読んだ。柳田翁や南方熊楠、折口信夫などが度々出てくるが、問題の捉え方は民俗学というより、文化人類学の視点に近い気がする。面白い。2024/02/28
もるーのれ
4
祭祀と供儀の関係性や歴史的な展開を、様々な文献史料・文学作品・民俗例などから丁寧に辿った1冊。鋭い指摘が多い。日本列島の「生贄」では、神への供物であると同時に神と人とが共食するものという特質があるという。山野河海の恵みの多い列島らしい考え方である。それが稲作を基盤とする国家体制の成立や仏教的な殺生禁断の観念が広まる中でも、非稲作社会を中心に命脈を保っていくのが興味深い。最後には柳田國男の言説にも触れられる。読破に時間は掛かったが、面白く拝読した。2025/05/03
tbsk
4
日本古来より存在していた「供犠sacrifice」の文化が、歴史の「大きな流れ(仏教、稲作、政治等)」によってどのように変わっていったか/変わらなかったかを、祭祀や物語を辿りつつ丁寧に記されており面白かった。特に「供犠の文化」と「供養の文化」の対比して、罪責に対してどう向き合ってきたかが語られるパートは作者の1番の熱が感じられて良かった。2022/07/03