内容説明
美術館で国宝を見てもなんだかピンとこないのは、感性や教養がないからではなく、作品との距離感や古びた色彩などにより作品が語りかける声が聞こえにくいから。本書では、国宝をはじめとした日本美術をデジタル復元で当時の色彩に戻し、制作された時の環境で鑑賞することで見えてくるストーリーを紹介。どんな作品も、はじめから国宝なのではない。ストーリーを理解することで感性がひらき、日本美術の鑑賞が自分のものになる!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
がらくたどん
61
時代を経てなんとか命を繋いだ文化財はもちろん最初から「国宝でござい」として創られたわけではない。そもそも中世・近世の古美術品の破棄・散佚に対して「古い物も取っておいた方がよくね?」と国レベルで動き出したのは明治4年。じゃあ「国宝」じゃなかったときの「それら」は何だったのかと言ったら、もちろん宗教・娯楽・暮らしの場で現役だった。高度デジタル技術で復元されたレプリカを往時の環境に近い形で眺めてみたら、ガラスケースに納められたオリジナル君からは聞こえにくい現役時の「それら」の言葉が聴こえるよという示唆に富む本。2024/03/08
ハル
7
どんな美術品もはじめから国宝として崇めるように鑑賞されていたわけではない、という当たり前のことに改めて気付く。オリジナルの色彩を再現し、さらに当時はこのように鑑賞されていたはず(屏風絵なら電球ではなく蝋燭の明かりで、近くに座ってやや見上げながらなど)というところまで再現してようやく、その本当の姿を見ることができるのは確かにその通りだと思わされる。著者が子供向けのワークショップとしてやっている鑑賞会に参加してみたい。絵巻物の見方も自分には目から鱗で、実際に手に取って読みたくなってしまった。2024/05/18
Keystone
5
国宝展つながりで。なるほど、確かに巻物は巻いてある状態で開き、巻きながら見てみたいものである。確かにコミックのよう。和歌の楽しみと繋がるというのも新鮮。デジタル復元した国宝をもっと見てみたい。 2025/05/20
果てなき冒険たまこ
5
正直に言いますが2020年に亡くなられた小林泰三(やすみ)さんが国宝について書いたんだと思って読み始めたら著者さんは小林泰三(たいぞう)さんでした(笑)でも本自体は抜群に面白く国宝をべたべたさわろうをコンセプトに活動するデジタル復元師さんが風神雷神図屏風だったり興福寺の阿修羅像だったり平治物語絵巻を最初はこうだったんじゃないかというところまで復元するわくわくな展開。国立歴史民俗博物館で見た当時を再現した青銅器を思い出してぜひ実物を見てみたいと思ったよ。2024/02/27
🍭
3
709(芸術政策、文化財)図書館本。光文社2023年12月30日発行。国宝鑑賞入門の本。2章の巻物=アニメ説と3章の桃山刺繍の部分は面白かったけれど、4章は今一つ。かなり柔らかいテキストで読みやすかった。2025/09/20
-

- 電子書籍
- Q&A日本経済のニュースがわかる! 2…
-
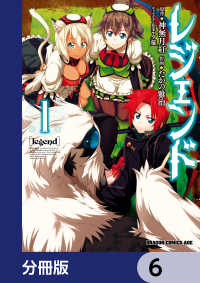
- 電子書籍
- レジェンド【分冊版】 6 ドラゴンコミ…
-

- 電子書籍
- 私のことなんか、どうせ。(11) コイ…
-

- 電子書籍
- 恋するハニー・バニー セット版4 G2…
-

- 電子書籍
- チャートで見る株式市場200年の歴史 …




