内容説明
都市に現れたヒグマたち
アイヌの人々に神と敬われ、豊かな自然の象徴とされながらも、しばしば駆除の対象ともなっているヒグマ。かれらはなぜ市街地に出没するようになったのか? 野生動物と人間の関係になにが起こっているのか? ヒグマの生態からその謎に迫る。
【主要目次】
序章 晩夏のヒグマの多様な素顔
第1章 北の森に暮らすヒグマの素顔
第2章 歴史的視点から見た人とヒグマの対立
第3章 農地への出没
第4章 市街地への出没
終章 これからのヒグマ管理
あとがき/引用文献
【序章より】
このところ、ヒグマの話題がつねに身近にある。私の身のまわりだけというのではなく、北海道全体でそうなのだ。毎年春になれば人身被害、初夏には市街地への出没や駆除の多発、晩夏には畑作物や果樹への食害、秋には果実類の凶作による餌不足と出没の関係が取り沙汰される。いったいヒグマになにが起きているのだろう。なぜ市街地に出没するのか、ほんとうに人とヒグマは共生できるのか、そのために私たちはどう対処すればよいのか。その答えはどれもそう単純ではない。地域によって、季節によって、年によって、ヒグマを取り巻く環境は変化し、人間社会も当然変化する。10年前と現在とでは人とヒグマの関係もまた違っている。
人とヒグマの関係についての答えは、絶滅か共存かの二項対立のなかにはない。人もヒグマも大切な地球の構成要素の一つとして50年後も100年後もともにこの地に暮らしていること、そのために一部の人が不安や負担を強いられない関係をめざす必要がある。いつの時代にも、どの地域にもあてはまるような一般的な解決策は存在しない。今起きていることを冷静に分析し、とりうる選択肢の最適な組み合わせはなにか、問題を抱えたそれぞれの地域がその時々に応じて考え決めていくべき問題だ。
冷静で効果的な判断のためには、ヒグマのこと、その他の野生動物や自然環境のこと、地域の人々の暮らしのこと、さらには地域以外の人々の考え方などをよく知り、地域の実情に応じていく必要がある。ヒグマについて、生息環境について、そしてそれを取り巻く地域について詳しく知れば、さまざまな場面で発生するヒグマに関わる問題を、他人事ではなく身近な関心事、自分事として共感を持ってとらえることができるようになるだろう。本書を手にとった方は少なくとも身近になったヒグマを知ろうと思ってくださったに違いない。本書が、さまざまな形で報道されるヒグマに関わる問題の背景にある、ヒグマという動物とそれを取り巻く環境、人との関わりのことを知っていただき、身近な動物として理解や共感を持っていただいたうえで、現在起きている問題の実態とその対処法について考えていただくきっかけになれば幸いである。
この本では、野生動物としてのヒグマの素顔と自然環境や人間の暮らしなどヒグマに関係する要素を取り上げ、生態学的視点から今なにが起きているのかを考察する。そして社会学的な視点も取り入れながら、今後の北海道におけるヒグマ管理について、そのあり方を議論したい。そのために、私のヒグマとの出会いから始まる約30年の足取りをたどりながら、ヒグマをめぐる旅におつきあいいただくことにしよう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
マリリン
まさ
taku
ちや
saladin
-

- 電子書籍
- ドライドンの曙 グイン・サーガ149 …
-

- 電子書籍
- 特命係長 只野仁ファイナル 愛蔵版 4…
-

- 電子書籍
- 令和川柳選書 暁花?
-
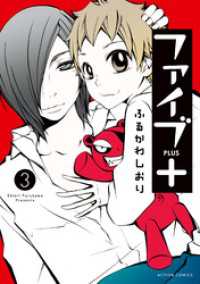
- 電子書籍
- ファイブ+ 3 アクションコミックス
-

- 電子書籍
- パープル式部 2 ヤングジャンプコミッ…




