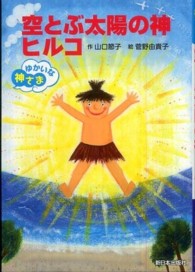- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
現代の私たちは日本の伝統文化をあまりにも知らない。それは明治時代に西洋の知識や技術を取り入れるためにつくられた学校教育や近代の学問が、日本の文学や歴史を私たちの心から切り離して論じてきたからだ。伝統的な日本人の心のあり方や死生観はどのようなものだったのか。いま私たちが伝統的と思っているものの多くが、いかにして明治に入ってからつくりだされてきたのか。民俗学や宗教学、倫理学等の観点から近代以降に日本人が見誤り、見失ってきたものを掘り起こす。
目次
序章 日本人の知らない日本の伝統/学校教育と近代の学問の問題点/文化と宗教の関係/神仏分離がもたらしたもの/「日本人は宗教的に寛容」か?/第一章 神のまつりと日本人/1 民俗学が目指したもの/柳田国男による民俗学の創始とそのねらい/民俗学者が明らかにした、日本の神のまつりの最も古い形/神のまつりと年中行事/神のまつりと日本の自然/神をまつる場所──日本とヨーロッパ/明治以前の人々にとって「カミ」とは?/「当たり前」は「当たり前」でない──現代の私たちと日本の神/サンタクロースは何者か?/2 柳田国男と折口信夫──二人の関心の違い/柳田国男と折口信夫の対立・相違点/折口信夫の歌の発生についての議論──信仰起源説/昔話に「昔」の社会を探る──男の仕事・女の仕事/歌の発達と歌垣/柳田国男の問題関心/折口信夫の問題関心──人はなぜ「あの世」を想定するか/「貴種流離」──物語の源流/『竹取物語』を読む/仏教についての柳田国男・折口信夫の捉え方/第二章 仏教と日本──古代から中世へ/1 仏教の伝来と展開/『日本書紀』の仏教伝来記事から「憲法十七条」へ/『日本霊異記』に見る伝来当初の仏教/神まつり・死者のまつりへの僧の関与/最澄・空海の果たした役割──仏教の全体像の紹介/親鸞や道元の教えは「やさしい」か?/源信『往生要集』の成功/2 神仏習合と中世の文化/伝統仏教の性格と神仏習合/中世の「芸道」/「日本は神の国」/第三章 新しい知の到来──近世・近代/1 中世から近世への転換/中国の儒教/キリスト教伝来前夜──戦国仏教(法華宗・一向宗)の台頭/キリスト教の伝来/宣教師の目に映った日本の仏教/中国におけるキリスト教布教──マテオ・リッチ『天主実義』/近世の思想状況/平田篤胤の神道説と幕末におけるその影響/2 明治維新から現代にいたるまで/新たな「日本の伝統」の創造/日清戦争・日露戦争の勝利とその影響/農村の疲弊/独創的な思想家たちの登場と敗戦/和辻倫理学を読み直す/超越と日常/あとがき/文献紹介
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
Mihoko
srmz
ひつじパパ
taq
-

- 電子書籍
- 転生したら序盤で死ぬ中ボスだったーヒロ…
-

- 電子書籍
- 女の覚悟 ひとり悩むあなたへ贈る言葉