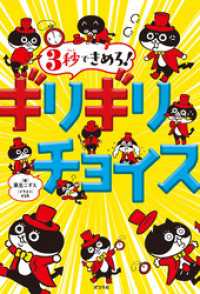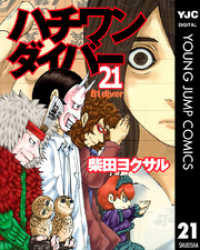- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
常に変化を求められながら、同時に変わらなさもあると感じる私たちの働き方。そもそも現代日本人の働き方の源流はどこにあるのだろうか。明治時代、産業革命以降の資本主義の流れのなかで形成されていったと見る向きもあるが、戦国時代の戦乱から解放され、おおいなる社会的・経済的発展や貨幣制度の成熟を背景に、多様化・細分化していった江戸時代の労働事情が、その源にあると本書では考える。当時の社会を形作ったあらゆる階層の働き方を丁寧に掘り起こしながら、仕事を軸に江戸時代を捉えなおす。
目次
はじめに/「働き方」は時代により変化する/江戸時代の「働き方」に注目する理由/歴史学の視点、経済学の視点/武士も町人も百姓も、トータルでみてわかることがある/第一章 「働き方」と貨幣制度/中世から近世へ──働き方の変化/身分の違いと「生活スタイル」/身分により固定化された「働く人生」/江戸時代の貨幣制度の発展/貨幣の種類と「使い方」/第二章 武家社会の階層構造と武士の「仕事」/武士のなかにある「序列」/地方知行制と俸禄制──武士の「収入」の方式2タイプ/武士の「家」と勤務の意識/「武」から「文」へ──武士の職分の展開/武士の学びと「役職」/第三章 旗本・御家人の「給与」生活/俸禄の実態/幕府米蔵からの給付システム/蔵米取の旗本・御家人の経済生活/御家人の「副業」/「役得」「贈答」も収入の一部/第四章 「雇用労働」者としての武家奉公人/泰平の世の到来と武家奉公人の変化/藩領域の武家奉公人/大名屋敷に雇われる武家奉公人/武家奉公人斡旋と派遣のしくみ/武家奉公人として送り込まれる百姓たち/第五章 専門知識をもつ武士たちの「非正規」登用/身分制に基づく政治運用の行き詰まり/経済官僚の台頭/専門家が登用される時代へ/旗本用人に求められる職業能力/幕末期の幕政改革と「非正規」登用された幕臣/第六章 役所で働く武士の「勤務条件」/役人に求められたもの/労働時間と休日/出勤状況の管理方法/役職手当と賞与/採用方法や役職就任手続き/幕府役人が「退職」する時/第七章 町人の「働き方」さまざま/少数派だった「正規雇用」/江戸の町人地と「町」/家持町人と「町」の関係/「裏店」のエリアと地借・店借層/「その日稼ぎ」の者の労働形態/江戸の奉公人・召仕の特徴/第八章 「史料」に見る江戸の雇用労働者の実態/人別帳からわかる江戸の町人の働き方/雇用労働者の実際/商家奉公人をめぐる法制度/日雇(日用)という労働形態の広がり/町人にとって理想の働き方/第九章 大店の奉公人の厳しい労働環境/「上方の本店」と「江戸の出店」/奉公人の人事制度/報酬の支給形態/奉公人の日常生活/大店の「定年制」をめぐって/第一〇章 雇われて働く女性たち/変化していく女性の社会的地位/商家における女性の役割/武家屋敷の奥女中奉公/町方の商家における下女奉公/乳母(乳持)──女性の特殊な雇用労働1/遊女屋奉公──女性の特殊な雇用労働2/第一一章 雇用労働者をめぐる法制度/触書・達と「御触書集成」/刑法における雇用労働者/奉公人が主人を訴えるということ/判例にみる雇用労働者の法的立場/豪商泉屋(住友家)の跡目騒動で問われた奉公人の責任/第一二章 百姓の働き方と「稼ぐ力」/「百姓」とは誰をさすのか?/租税の特性と労働形態/さまざまな商品作物/農村における日雇労働/農間余業でさらに稼ぐ/第一三章 輸送・土木分野の賃銭労働/戦国時代までの陸上輸送/江戸時代の宿駅制度と商い荷物輸送/河川舟運と百姓の農間稼ぎ/幕府・藩の治水事業と百姓の賃銭労働/第一四章 漁業・鉱山業における働き手確保をめぐって/海の労働世界、山の労働世界──集約的労働の場/漁業の人手はどのように確保されるか?/鉱山で働く人々、「働かされた」人々/大量雇用の時代へ/おわりに──近代への展望/あとがき/参考文献一覧(主要なもののみ、引用順)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
きみたけ
ヒデキ
うえぽん
よっち