内容説明
メイドは玉の輿に乗れるのか?
19世紀イギリスのミリオンセラー『ビートン夫人の家政書』によると、社交界では家庭の主婦が集まれば使用人の愚痴に夢中になったという。では、それはどんな愚痴だったのか?
本書では、伝統的な使用人がどのように文学作品に表われているかを考察しつつ、使用人についての記録やハンドブックなどを参照して、イギリス文化と文学における使用人のイメージとその実態(と、愚痴の生まれる社会的背景)を比較分析する。
下男の章で、ディケンズ『荒涼館』に登場する刑事が、屋敷の下男に対する聞き込みの際に、「下男にとって理想的な出世コース」をたどった父親の話をして親近感を抱かせる話が紹介されるが、Uブックス化にあたって新たに追加された「『使用人』ではない被雇用者たち」の章では、オースティン『自負と偏見』で、ウィカムがリジーに対して父親のまさに同じような話をして取り入るくだりが解説され、興味深い。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
121
日本の執事について日経流通新聞に記事が出ていたので興味を持った。本場イギリスの使用人には家令から庭師、ハウスキーパーからメイドまで明確な階級があり、仕えている家の事情により仕事や待遇が明確に分かれて働いている事情が見えてくる。身分の低い料理人でも主人の胃袋を摑めば結婚できたり、母親より自分を育てた乳母に愛情を感じる話が英米文学でしばしば出てくるのも納得できる。こうした長年の伝統から成立した使用人像は、ジーヴスやクリスティを読む際に参考になる。使用人などに無縁な小市民としては、ファンタジーにしか思えないが。2024/04/28
よっち
39
使用人記録やハンドブックなどを参照して、伝統的な使用人がどのように文学作品に表われているかを考察しつつ、イギリス文化と文学における使用人のイメージと実態を比較分析する一冊。社交界では淑女たちが夢中になった使用人に対する愚痴。執事やハウスキーパー、料理人、メイド、従僕と下男、乳母といった役割がどんな立ち位置だったのか、当時の時代背景も絡めながら解説していて、下男は身長や見栄えの良さが思っていた以上に重要だったこと、男どもの誘惑が多いメイドの立ち回りの重要性など、いろいろ大変だなと感じつつ興味深く読めました。2023/09/25
makko
7
メイドと執事から、ハウス・キーパー、料理人、従僕、下男、ガヴァネスにナニー、ランドスチュワードまで、イギリスの使用人について説明した作品。ダウントン・アビーが大好きなので、イメージがわきやすく楽しく読みました。英文学からの引用を使った説明も多く、なんとなくわかったような気で読んでいた使用人それぞれの位置付けや階級社会の中の立場がわかっておもしろかったです2024/07/25
あらい/にったのひと
2
神保町ブックフリマで買ってきた本。18-19世紀の実態と、それに対する20世紀以降の印象や扱いなどを簡単にまとめた本。わかりやすさが新書サイズに合っていてよい。白水社なので巻末に参考文献がまとまっているので、入口としてとてもよい本ですね。2024/05/24
サトー
0
階級の話だった。2023/12/14
-

- 電子書籍
- 赤騎士は金の亡者になりません【タテヨミ…
-

- 電子書籍
- 社長の特別命令【タテヨミ】第23話 p…
-

- 電子書籍
- 【単話版】北政所様の御化粧係~戦国の世…
-
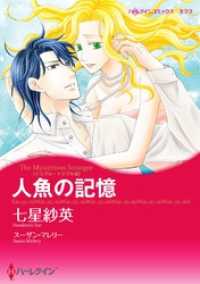
- 電子書籍
- 人魚の記憶〈トリプル・トラブル III…





