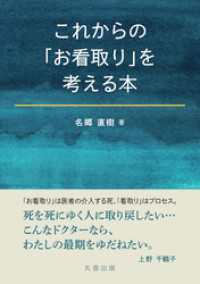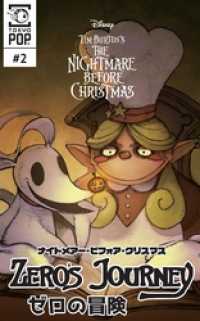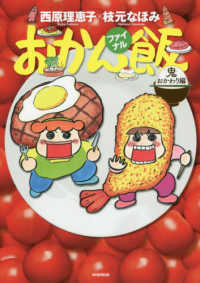内容説明
松之廊下にはどのような役割があったのか? 老中の登城から退出までを追ってみると?「奥」の側用人が「表」の老中より権力をふるえたしくみとは? 大名統制において殿中儀礼が持った意味とは? 大奥女中にはどのような仕事があったのか? 江戸城における政務は、本丸御殿の構造と密接に関係している。部屋の配置とその役割を詳しく紹介し、「表」「奥」「大奥」それぞれで展開した幕府政治のしくみを読み解く
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
紙狸
20
2008年刊行。江戸城という空間の分析を通して、権力を巡る人間関係を描いたと言えるだろう。徳川家康はいくさに勝ち抜いて幕府を開いたが、いくさがなくなったあとの幕府というのは、なんと煩雑な序列で構成されていたのか。寺社奉行・大岡忠相の日記によると、職務に関して将軍吉宗と謁見したのは7年間で14回に過ぎないという。正式なヒエラルヒーの中では将軍に会うのが大変なことだったのだな。2022/01/15
MUNEKAZ
15
江戸城本丸御殿を「表」「奥」「大奥」に分けて解説した一冊。図版や資料が多数引用されており、将軍権威と大名たちの序列が計算された「表」の空間設計や、将軍の生活の場であり、同時に側近政治の現場でもある「奥」の生々しさがよくわかるようになっている。ドラマなどでは省略されているが、将軍や御台所にはどれだけお付きの人物がいたか、またその手当はどれだけだったのかなど、細かい部分までわかるのが面白い。読み物としては少々趣きに欠けるが、時代劇や時代小説のお供にすれば、時代背景や制度への理解が深まるだろうと思う。2021/11/12
mahiro
8
江戸城本丸御殿の詳しい見取り図と解説、登城する大名達の身分により分けられた拝謁場所などの細々とした決まり、老中や側用人などが御殿内のどの場所でどのようにして政の協議や将軍への意見具申をしていたのか、更には将軍の身の回りに仕える者達の人数や大奥で夫人や生母に当てられた召使いの人数や分類や報酬など詳しく書かれていて実に面白かった。江戸城関係の本は他にも読んでいるが本書はその中でも内容が濃い方だ、畳一枚座る位置の違いで序列がわかるその形式も平和な時代の秩序の保ち方なのだろう、時代小説を読むとき役に立つと思う。2017/03/28
OjohmbonX
5
江戸城本丸御殿のレイアウトと徳川幕府の政治システムをリンクさせて丁寧に解説する本。玄関から向かって表→奥→大奥と公→私の階層分けがされてて、例えば表の中も黒書院→白書院→大広間と玄関に近いほど公的なレベルが高い。一番面白かったのは、最初から有力大名を幕政から疎外(役職に就けなく)して官位だけ与えておいて、しかも官位を毎年の行事の席次と結びつけて他人との上下を意識させお互い競争させて、昇進のために金(工事費や賄賂)を出させて弱らせる仕組み。後は皇家公家コントロールのシステムのこれくらい手軽な解説書ほしいな。2014/05/24
J309
4
江戸城本丸御殿の構造を、幕府の政治構造とリンクさせて語るとというのが興味深い。 例として、幕政の中枢たる老中達が詰める御用部屋が、大老堀田正俊の刺殺事件後に将軍の居室近くから離れた場所に移ったが、幕府の政治体制が老中合議制から将軍独裁制に傾いていた事と関連していると推定している。 そういった具合で、儀式・政治空間である"表"から将軍の私的空間である"奥"、そして女性達の生活空間である"大奥"について、各項目が短いページ数でまとまっていて江戸城本丸御殿の機能について網羅的に分かるし良い本だった。2014/10/11