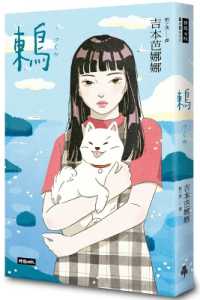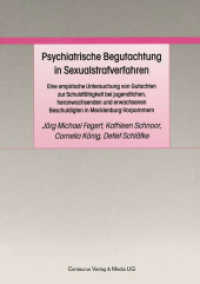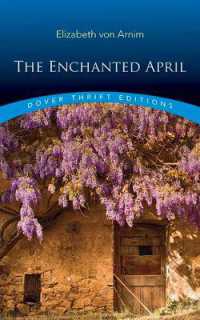内容説明
日本人はなぜ、いつ、「読者」になったのか? そして何を、どのように、読んできたのか?
出版資本と鉄道による中央活字メディアの全国流通、旅行読者の全国移動、新聞縦覧所と図書館という読書装置の全国普及――官・民による、これら三つの全国的要素の融合から、明治期に活字メディアを日常的に読む習慣を身につけた国民、すなわち「読書国民」が誕生してくる過程を、出版文化研究の第一人者が活写。私たちの読書生活の起源がここにある!
[目次]
はじめに
■第一部 流通する活字メディア
第一章 全国読書圏の誕生
第二章 「中央帝都の新知識」を地方読者へ――新聞社・出版社による地方読者支援活動の展開
■第二部 移動する読者
第三章 車中読者の誕生
第四章 「旅中無聊」の産業化
■第三部 普及する読書装置
第五章 読書装置の政治学――新聞縦覧所と図書館
第六章 図書館利用者公衆の誕生
あとがき
学術文庫版へのあとがき
[主なトピック]
○暴力沙汰まで! 「東京vs.大阪」新聞市場争奪戦争
○過疎地域を開拓せよ! 新聞社・出版社による地方読者支援活動
○駅は戦場! 漫画雑誌の隆盛はここから始まった
○お部屋訪問! 温泉地の貸本屋
○「情報にお金を払う」習慣を生んだ新聞縦覧所
○自由民権運動は下からの「読書国民」の創出
○読書の価値を再発見した日清戦後の一等国意識
○まるで監獄……帝国図書館の規律空間
○樋口一葉も友人と……女性が一人で行けない図書館
目次
はじめに
■第一部 流通する活字メディア
第一章 全国読書圏の誕生
第二章 「中央帝都の新知識」を地方読者へ――新聞社・出版社による地方読者支援活動の展開
■第二部 移動する読者
第三章 車中読者の誕生
第四章 「旅中無聊」の産業化
■第三部 普及する読書装置
第五章 読書装置の政治学――新聞縦覧所と図書館
第六章 図書館利用者公衆の誕生
あとがき
学術文庫版へのあとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
朗読者
シルク
緋莢
manabukimoto
iwasabi47
-
- 洋書
- Thrush
-

- 電子書籍
- 虹色パンツ 19歳・童貞の僕が飛び込ん…