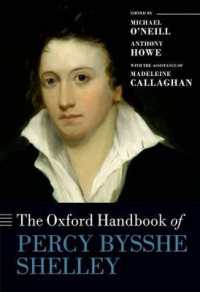内容説明
納豆はご飯のおかず? 調味料? 味噌、醤油と並んで和食に欠かせない納豆は、アジア全域でもおなじみのソウルフード。でも各地の納豆を見れば、トウチや魚醤と同じく調味料としてや、チーズがない時期の代用品として使われたり、植物の葉や段ボール箱の中で自然発酵させたり……地域によって納豆の姿はさまざま。日本では、かつて「ハレ食」だったのが、現在は健康食として、伝統食材としても見直され始めています。 地域や時代につれて変遷をとげる「アジア・日本の納豆」の深い世界を、豊富な写真や図版とともに伝えます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イトノコ
25
図書館本。日本の納豆の歴史と、アジア各国の納豆文化について解説。/アジア納豆についての報告は高野さんと同じだが、日本の納豆が戦後の食中毒事件をきっかけに稲藁か廃れて機械化されていく歴史や、かつて東北では年末年始のハレの食事だったという民俗学的な記事が興味深い。しかし日本の中世までの記録では、糸引き納豆(枯草菌発酵)なのか塩納豆(麹菌発酵)なのか分からないものが多いのだとか。もしかして韓国のチョングッチャンのように、昔は枯草菌と麹菌両方で発酵させていたのが、江戸時代くらいに分離したのでは…高野さん説的には。2022/01/24
ようはん
16
納豆関連の本はいくつか読んできてアジア方面にも納豆があるのは知ってはいたけど、大豆ではなくピーナッツを使用したり発酵に藁ではなくシダを使用したりと日本にしろアジア諸国にしろ納豆文化はここまで多様性があるのかと感じた。2021/09/22
kenitirokikuti
6
道の駅しょうなん(千葉県柏市手賀沼の岸辺)のブックコーナーにて。高野秀行のアジア納豆本を読んでたのだが、本書が目に入る。日本列島あたりだと、照葉樹林帯と針葉樹林帯の境目が語られたりするが、インドシナ半島の旨味圏は大きく3つに分けられる。魚醤圏(魚がたくさん漁れるので漬けて保存)、穀醬圏(味噌や酒など)、チベット方面のチーズ。そして、その交点あたりに納豆圏がある。なお現代日本の納豆は大豆と藁から分離培養された納豆菌だけで生産されるが、元は大豆と何らかの植物を原料とする。なお、納豆菌はサルモネラ属菌を殺さない2022/09/19
Hiroki Nishizumi
3
納豆は日本独自の食文化ではなかったこと、ハレの日に出されていたものだったこと、納豆菌というものはないこと、など参考になった。いろいろ先んじて調べている人がいるものだ。2021/08/17
chuji
3
久喜市立中央図書館の本。2021年6月初版。初出Webサイト「のう地」2020年6月~12月。加筆・修正と書き下ろし。オイラは毎晩納豆を食する。図書館の新刊コーナーにあったので借りた本。納豆は奈良時代からあり、昭和初期迄はハレの日の食べ物だったとのことです。亜細亜では色々な納豆があるのです。2021/07/18
-

- 洋書
- Réalité v…