内容説明
何をするべきかを自分で意思決定し、能動的に行動する能力、それが「行為主体性」だ。
生物はどのようにして、ただ刺激に反応して動くだけの存在から、人間のような複雑な行動ができるまでに進化したのか?
太古の爬虫類、哺乳類、大型類人猿、初期人類の四つの行為主体を取り上げ、意思決定の心理構造がどのように複雑化していったのかを読み解いていく。
進化心理学、進化生物学、行動生態学、認知科学など、これまで別々に取り上げられることの多かった人間と動物の研究をまとめ上げ、包括的な行為主体のモデルを提唱し、その進化の道筋を解明する画期的な新理論。
◆賞賛の言葉◆
「説得力があってわかりやすい、すでに古典というべき書。科学を前進させ、人間の本性を学ぶ次世代の学徒に読み継がれることだろう」
――ブライアン・ヘア(デューク大学進化人類学教授、『ヒトは〈家畜化〉して進化した』著者)
「心理学の第一原理は心理や行動ではなく、行為主体性であるべきだという斬新な洞察に満ちている」
――デイヴィッド・バクハースト(カナダ・クイーンズ大学卓越教授)
目次
第1章 はじめに
動物心理に対する進化生物学的アプローチ/人間の心理に対する進化的なアプローチ/本書の目標
第2章 行為主体のフィードバック制御モデル
行為主体の機械モデル/生態系が課す問題のタイプ/絶滅種のモデルとしての現存種
第3章 目標指向的行為主体――太古の脊椎動物
生きた(非行為主体的)アクター/目標指向的行為主体/生態的ニッチと経験的ニッチ/行為主体の基盤
第4章 意図的行為主体――太古の哺乳類
情動、認知、学習/実行層/行動実行に関する意思決定/実行(認知)制御/道具的学習/自己の目標指向的な行動や注意の経験
第5章 合理的行為主体――太古の類人猿
社会生態的な難題/因果性の理解/意図的な行動の理解/合理的な意思決定と認知制御/反省層とその経験的ニッチ/だが大型類人猿はほんとうに合理的なのか?
第6章 社会規範的行為主体――太古の人類
初期人類の協働における共同的行為主体性/共同目標を設定する/役割の連携/協力し合いながら協働を自己調節する/協力的合理性とその経験的ニッチ/文化集団における現生人類の集合的行為主体性/集合的な目標の形成/社会的役割の連携/社会規範を介しての集合的な自己調節/規範的合理性とその経験的ニッチ/人間の行為主体性の複雑さ
第7章 行動組織としての行為主体
補足説明A
補足説明B
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テト
Gokkey
月をみるもの
mim42
Yoshi
-

- 電子書籍
- 麗しき名医・九卿【タテヨミ】第75話 …
-
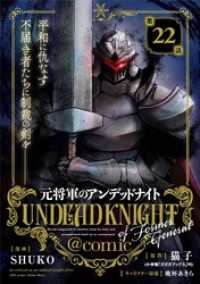
- 電子書籍
- 元将軍のアンデッドナイト@comic(…
-
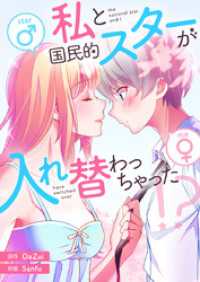
- 電子書籍
- 私と国民的スターが入れ替わっちゃった!…
-
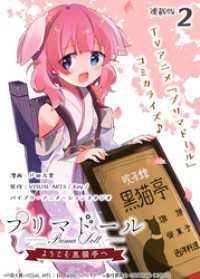
- 電子書籍
- プリマドール ~ようこそ黒猫亭へ~ 連…
-

- 電子書籍
- こはく色の夢【ハーレクインSP文庫版】…




