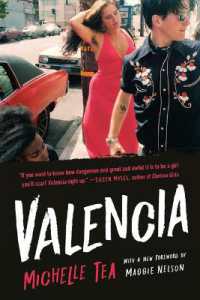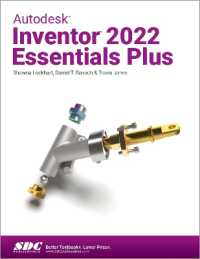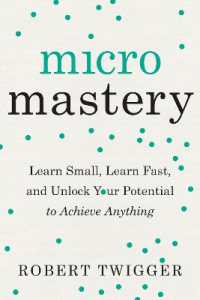内容説明
フランスのアナーキスト、ピエール・ジョセフ・プルードンは言った、「法律は、金持ちにとっては蜘蛛の巣。政府にとっては漁網、人民にとってはいくら身をよじっても脱けられない罠」だと。まさに今の日本の状況そのものじゃないか! 【目次】第1章 ルールは何のために生まれたのか…さまざまな局面に則して多様なルールが作られた/第2章 ルールとして成り立つ必須条件…人は自分が損をしてでも公平さを求める/第3章 フェアプレーの精神…ルールに反してなければいいのか?/第4章 時代に応じて変わるべきルールもある…いつまで異性同士の結婚にこだわる?/第5章 復讐するは誰にあり?…世界が滅ぼうとも刑は執行されねばならない/第6章 なぜ人々は立ち止まらないのか…利己的な人々が自ずと社会秩序を作る/第7章 こんなルールは嫌だ!…中途半端なルールは混乱を生む/第8章 民主主義は公正じゃない…多数決は根拠のない偏見までも温存する
目次
はじめに/真面目な国民は「要請」を守る/権力者や金持ちは法律すら守らない/第1章 ルールは何のために生まれたのか/平常時のルール:世界や社会を円滑に回す/弱者を優先して救済するためのルール/資源に限界がある場合のルール/国家や社会の崩壊時には「自分が生き延びる」ルール/生き延びるために他人を蹴落としてもよいような状況/第2章 ルールが成り立つ必須条件/法律を学ばずとも、大抵の人々は平和に暮らす/ルールの拘束力は嫉妬心だ/ルールの原点/第1次的ルールと第2次的ルール/誰から見ても決して許せないことって何だ?/なぜ国民は政府や知事のいうことをきかなかったのか/人は自分が損をしてでも公平さを求める生き物だ/公平なルールをいったん受け入れたならとことん守ろうよ/公共性と普遍性が必要/いつでも、どこでも、誰にでも通用するルール/ただ、普遍性も貫きすぎると……/第3章 フェアプレーの精神──ルールに反していなければいいのか?/「俺を踏み台にしたぁ!?」/反則をしない限り、勝つためには何をしてもよいのか?/経験に基づく合理的なルール/フェアプレーの義務/スポーツ仲裁裁判所の裁定はいいのか?/逆に選手を追い込む最低の裁定/そもそもドーピングは悪だろうか?/第4章 時代に応じて変わるべきルールもある──たとえば結婚/いつまで異性同士の単婚制にこだわる?/同性婚やパートナーシップ制を認めればそれでいいのか?/なぜ複合婚がいけないの?/反婚の思想/異性間単婚制を肯定する意見を批判する/初音ミクと結婚した男性/家族を作るとはどういうことか?/第5章 復讐するは誰にあり?──報復のルール/死体を処刑!?/世界が滅ぼうとも、刑は執行されねばならない/刑罰の起源は復讐/「餓死したくないから罪を犯す」の連鎖/復讐を止める裁判/刑罰の条件/裁判制度があっても、復讐は消えない──キャンセル・カルチャー問題/復讐するは誰にあり?/とはいえ……/第6章 なぜ人々は立ち止まらないのか──法律でも変えられないルール/小便小僧、存続の危機?/慣習とルールを分ける3つのポイント/エスカレーターで人々が立ち止まらないわけ/原因1 ハートのいう「ルール」になってしまっている/利己的な人々が自ずと社会秩序を作る/原因2 赤の他人の事情より、自分が急ぐ都合が優先/原因3 ナッシュ均衡が成立してしまった/ルールが変わる条件/片側は譲るが、席は譲らない──「優先席」という悪しきルール/なぜ男性は座って用をたすようになってきたのか/ゲーム理論を参考にすれば定着したルールを変えられる/第7章 こんなルールは嫌だ!──ダメなルールの特徴/なぜマスクは「必須」から「個人の判断」に転じたのか/曖昧な「個人の判断」「お控えください」/中途半端なルールは混乱を生む/半端なルールが「警察」を出現させる/外国人の視線がそんなに気になる?/他人がマスクを着けようが着けまいが、もともとどうでもよかったのではないか?/「大切な人」を人質にとるルールのイヤらしさ/第8章 民主主義は公正じゃない/特定の層におもねる政治や立法はダメ/法や政策は無差別公平でなければならない/多数決は根拠のない偏見までも温存する/スーパーアイドルがお笑い芸人に人気投票で負ける理由/民主主義は諸刃の剣/おわりに/清濁併せ むのがルールである/毒も栄養も喰らうのが人間である/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
venturingbeyond
kei-zu
ta_chanko
takka@ゲーム×読書×映画×音楽
-
- 洋書
- Valencia