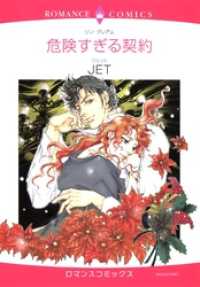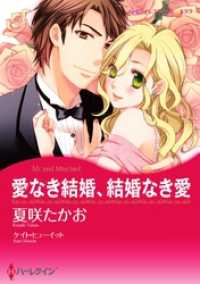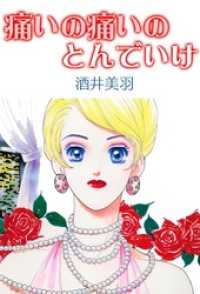内容説明
劇場のように華やかな装飾。高い天窓からふり注ぐ陽光。シルクハットで通勤するしゃれた従業員。乗合馬車で訪れる客を待つのは、欲望に火を付ける巨大スペクタクル空間!
帽子職人の息子アリステッド・ブシコー(1810-1877)と妻マルグリットが、様々な施アイデアで世界一のデパート「ボン・マルシェ」を育て上げた詳細な歴史を、当時を描く仏文学作品や、19世紀初頭のデパート商品目録など稀少な古書から丹念に採取。
パリの世相や文化が、いかに資本主義と結びつき、人々の消費行動を変えていったのか、
仏文学者にして古書マニア、デーパート愛好家の著者だから描けた、痛快・ユニークなパリ社会史!
内容紹介)
客の目をくらませてしまえ!世界だって売りつけることができるだろう!
「白物セール」のときには、それぞれの売り場が白い生地や商品だけを優先的に並べたばかりか、上の階の回廊や階段の手擦りを白い生地で覆いつくし、造花も白、靴も白、さらに家具にも白のレースをかぶせるなど、全館をすべて白で統一し、
1923年の「白物セール」では、「北極」というテーマに従って、アール・デコ調にセットされたシロクマやペンギンが、ホールに入った客を出迎えるようになっていた。
ようするに、ブシコーにとって、店内の商品ディスプレイは、〈ボン・マルシェ〉という劇場を舞台にして展開する大スペクタクル・ショーにほかならなかったのである。
――第二章「欲望装置としてのデパート」より
*本書は『デパートを発明した夫婦』(講談社現代新書 1991年11月刊)に「パリのデパート小事典」を加筆し、改題したものです。
目次
まえがき
第一章 ブシコーとデパート商法
昔の商店/買い物はいやいやするもの?/マガザン・ド・ヌヴォテの登場/社会的条件の整備/ウィンドー・ショッピングの快楽/ブシコー青年、パリに上る/衝撃の出会い/マガザン・ド・ヌヴォテの新商法/何も買わずに出られない/現金販売と直接仕入れ/ブシコー、〈ボン・マルシェ〉の経営者となる/薄利多売方式の採用/流行を自らの手で作りだす/大企業の論理/バーゲン・セールの発明/「ニッパチ」をどうするか/「白」の展覧会――大売り出しの始まり/大売り出しの年間スケジュール/「目玉商品」というコンセプト/値引き合戦の軍配/「誠実」が最高の商品――返品可
第二章 欲望喚起装置としてのデパート
巨大店舗の建設/スペクタクル空間の創造/光り輝くクリスタル・ホール/ブシコーの魔法にかけられて/万国博覧会とデパート/商業のカテドラル/演出された大混雑/人の流れを支配せよ!/商品のオペラーーディスプレイ/客の目をくらませてしまえ/女の征服/賢い主婦の買い物/いい買い物をしたという充実感/贅沢品の誘惑/万引きを誘発するデパート
第三章 教育装置としのデパート
ライフ・スタイルの提唱/欲望の掘り起こし/〈ボン・マルシェ〉学校/ヴァカンス教育/ステイタス・シンボルとしての子供/子供の夢の国/「広告」という教科書/〈ボン・マルシェ〉アジャンダ/ピンク・ページの情報戦略/アッパー・ミドルをめざせ/景品による子供の教育/新聞記事の活用/万国博の利用/読書室による集客戦術/文化戦略の始まり/従業員によるクラシック・コンサート/「下部構造」への配慮ーーサニタリー・スペースの充実/無料のビュッフェ/カタログによる通信販売/総売り上げを上まわる通販の伸び率/とにかく、商品を見せてしまえ/デパートを発明した夫婦
第四章 管理の天才、ブシコー
独立売り場制/商品の到着/ゲルト制度/弱肉強食の世界/店員の理想像と本音/新しい労使関係/マニュアル化された店員教育/「会計に行く」はクビのこと/昇進システムの確立/売り場主任の望みは取締役/ブシコー未亡人の決断/サラリーマン人生の誕生/福利厚生制度確立の誓い/ガルガンチュアの厨房――無料の社員食堂/したたかな計算/快適な独身寮も無料/店員の意識改造/外観のブルジョワ化/男子はシルクハットをかぶること/店員むけ教養講座の開設/連帯感というメリット/従業員の差別化/ホワイト・カラーの成立/当時は異例の定期昇給/その他の労働条件
第五章 利益循環システムとしての福利厚生
社内貯金のすすめ/退職金制度の設立/フランス中を感動させた養老年金制度/利益循環サークルの完成/ブシコー夫妻と三千人の子供たちの店/慈善活動と社会還元/デパートの発明と現代社会――結論にかえて
パリのデパート小事典
あとがき
学術文庫版あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ごへいもち
さとうしん
miaou_u
ろべると
Wataru Hoshii