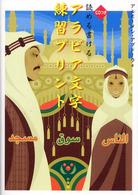内容説明
日本のゲーム研究を牽引する著者の主要論考をすべて集成
電子回路をもつゲームであるデジタルゲームを知覚や認知、ゲームプレイ、メディア、音、eスポーツ、文化資源などの視点から多面的に論じつつ、さらには大塚英志と東浩紀による「ゲーム的リアリズム」論争をも詳細に跡付ける、日本のゲーム研究を牽引する著者によるゲームを考えるための必読文献。
【主要目次】
序 ゲーム研究とはどういうものか
I 知覚と認知――プレイヤーはゲームをどう感じるのか
第1章 スクロール
第2章 視点と空間
第3章 ゲーム空間の記号学――二重化する知覚
II ゲームプレイ――プレイヤーはゲームをどう遊ぶのか
第4章 ゲームプレイと他者への信頼
第5章 カウンタープレイ――ゲームに抗うプレイヤー?
第6章 ゲームと公平性――社会革新としてのプレイ
III メディア――コンピュータで遊ぶ/コンピュータを遊ぶ
第7章 プレイヤーとキャラクター――ゲームにおける死の問題
第8章 メタゲーム――自己批評するゲーム
第9章 メディアとしてのゲーム
IV 文化のなかのゲーム――多面化するゲーム研究
第10章 ゲームと音・音楽
第11章 eスポーツはスポーツなのか
第12章 ゲームの文化資源学
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おっとー
6
ゲーム研究の端緒となる本。論集のため一つ一つのトピックが深堀りされているわけではないが、ゲームにおける視点・高さ・スクロールなどの工夫、ハイスコアといった他者的存在、メタゲーム(ゲームの中のゲーム)などの論点が散りばめられていて、ゲームを巡る視点の多様さを知ることができる。なんとなくだけど、ゲームは作り手も細かいネタや表現を散りばめられるし、受け手も制約プレイや裏技探しなど、本来のルールから逸脱した操作をすることができる。言ってみれば、作者-消費者双方にとって自由度の高いメディアなのかもしれない。2024/03/31
じーーーな
3
著者によるデジタルゲーム研究関連の論文12本を改稿してまとめた本。1冊の本としても読める体裁になっているが、デジタルゲーム研究のあらゆるトピックについて網羅的・体系的に学べることを目指した本ではなさそう。あとがきにも書かれている通りゲームについて語るのってめちゃくちゃ楽しいのだけれど、その際に「誰かが一度考えた道筋」を知っておくことはより実のある話をするためのガイドになるし、ひとによってはそこから先の地平を切り拓くこともできるかもしれない。2023/10/10
たろーたん
2
ゲームや漫画などサブカル系のこういう本を見ると、いつも挫折する。面白くないのだ。著者は東大の先生で、音楽学の本でサントリー学芸賞も受賞しているすごい人だ。それなのに、なぜこうも私に嵌まらないのか。私の感想だが、アニメ、漫画、ゲームなどのサブカルは社会学や文学ではなく、哲学にくっついてしまっている気がする。そのため、カルチュラルスタディーズのように「どのように受容されているか」や「どのように記号・解釈されている」かの話にはならないし、文学のように解釈の面白さ、読みの豊かさみたいな方向にも行かない。(続)2024/09/07
halow
1
これは面白い。著者がこれまでビデオゲームについて論じた文章をまとめた本だが、著者の関心と知識の広さのためか話題が幅広く、ここからさらに議論を広げられそうな問いかけがいくつもあった。 個人的には5章がとりわけ興味深い。同じ規則を共有する人間同士でなければゲームは成立しないが、それと同時にその規則を逸脱する瞬間こそ我々が最もゲームへ期待しているものなのではないか、ということを考えた。2025/03/28
いたる
0
普段からゲームと文芸の違いは何か?を考えている自分にとっては実りある時間だった。2023/11/21
-

- 電子書籍
- ワケあり婚9 NETCOMICS