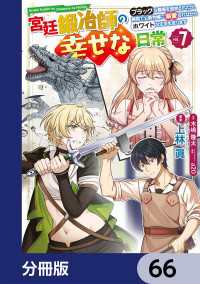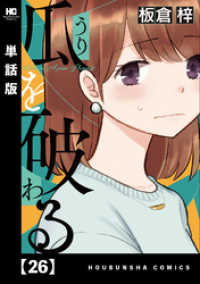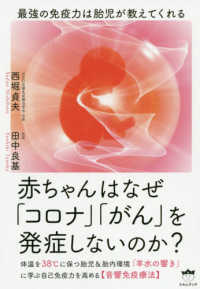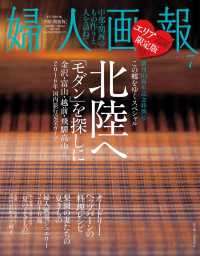- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
二百六十五年の平和――その体制を徳川家康がつくり上げることができたのは、波瀾万丈の人生と、天下人織田信長・豊臣秀吉の「失敗」より得た学びがあったからだった……。しかし盤石と思われたその体制は、彼の後継者たちによって徐々に崩され、幕末、ついに崩壊する。なぜ、徳川政権は消えてしまったのか? 薩長による明治維新は最後のトドメにすぎない。家康の想定を超えて「誤算」が生じ、徳川政権が滅んでしまったウラ事情をわかりやすく解説! そして、家康が「日本のつくり」に与えた影響とは――。 ●第一章 家康はなぜ、幕藩体制を創ることができたのか ●第二章 江戸時代、誰が「神君の仕組み」を崩したのか ●第三章 幕末、「神君の仕組み」はかくして崩壊した ●第四章 「神君の仕組み」を破壊した人々が創った近代日本とは ●第五章 家康から考える「日本人というもの」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
153
徳川の天下を長く保つため、信長と秀吉に学んだ家康は様々な仕組みを構築した。しかし戦国の遺風を残す改易や人質などの諸制度を後継者が社会情勢の変化に合わせて緩和したため、大名は幕府を恐れず自らを王臣と意識するようになる。一方で家康の決定ではない鎖国は固守したが、外国の情報や最新技術の導入が遅れて幕末の迷走を招いた。表面的な平和に馴れた歴代幕府首脳が、政治の厳しさを忘れ現状維持を最優先するようになった結果だ。さらに太平の世で文化が成熟して、現代まで続く日本人の気性が生じた。家康の誤算が歴史と日本人を生んだのだ。2024/03/03
とん大西
107
家康の誤算…。現代日本から振り返ってみれば、それは正なのか負なのか。江戸のミラクルピースは家康も想定外の結果往来か。幸か不幸か三代家光の頃、機能し出した譜代による官僚機構がその後の日本のテンプレートに。幕政も維新政府も戦前戦後も。良くも悪くもですが。我々の思想や思考の土台は、祖先の記憶が連綿と紡がれた泰平の御世に形成されたんだろうと思います。と、なると、誤算どころか家康の事跡は壮大過ぎてはかりしれないものがあります。(こういうの読むと、ちょいとしゃっちょこばってまう(^o^;))2024/02/13
さつき
70
徳川家康が作った江戸幕府による支配がどのように作られ、そして時代に合わなくなると変化し、やがて崩壊していったか。その過程が描かれています。主には幕末や明治期の話し。様々なちょっと意外なエピソードが散りばめられていて楽しく読みました。2024/08/15
たいぱぱ
67
265年もの間続いた徳川幕府の仕組みを家康がどう作り上げ、そしてどうして崩壊していていったかを磯田さんが噛み砕いて優しく教えてくれます。とはいえ、僕にはわかったようなわかってないような…。ただ明治維新が薩長だけがやった訳ではなく、むしろ旧幕府の優秀な人材が近代化を成し遂げたなんて面白い。「正直」「勤勉」が江戸時代が作り上げた日本人の美徳だとすると、現代の日本に今も影響を与えているんですね。磯田さんが歴史家として一貫して主張してるのは「歴史の失敗で学べ」ということ。本作もそれが主眼かもしれません。2025/08/27
森林・米・畑
60
なぜ幕府が壊れたかを、様々な視点から見ていく。徳川家康は幕府を開き、永続するシステムを考えた。結果、平和な時代が260年続くが、システムの老朽化(時代とともにそぐわなくなる)が響く。また家康のシステムを後世の将軍や老中などが良い方に変えたりもしたが、悪い方に変えた事が幕藩体制を崩す事になった。分かりやすく読みやすかった。2023/11/19