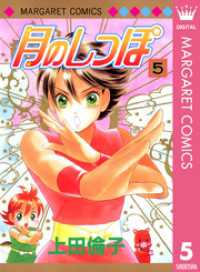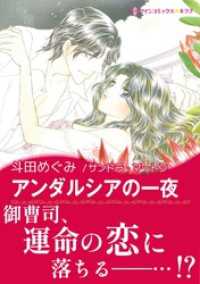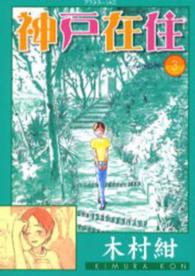内容説明
記念すべき第1回音楽本大賞の「大賞」&「読者賞」をダブル受賞!
「録音」が開く、聴覚の新たな地平
木々のざわめきに、都市の喧騒に、民族音楽の背後に、固体を伝う振動に、水中の音環境に、私たちは何を聞き取ることができるのか?
実践と鑑賞を通じて、音の可能性を拡張する画期的音響文化論!
2000年代以降、小型軽量で廉価なデジタル・レコーダーの登場、そしてSNSの台頭により、フィールド・レコーディングという言葉を目にする機会がますます増え、「音」や「聴くこと」について人々の関心が高まりつつあります。
フィールド・レコーディングは、現代音楽やサウンド・アートの文脈、60年代末からつづくサウンドスケープと環境音楽、90年代では音響派ブームのなかで取り上げられる機会の多かった音楽ジャンルであると同時に、人類学・民族音楽学などの学術の領域での研究手法として、また電車や野鳥の録音をするような趣味としても広くおこなわれてきたものです。しかし、こうした文脈をまとまった形で取り上げ解説される機会は多くはありませんでした。
フィールド・レコーディングには響きとしての音楽的な面白さだけでなく、その音が生じる場所の歴史や生態環境、録音者の視点といった文脈が深く結びついています。本書は、こうしたフィールド・レコーディングが歩んできた様々な文脈を統合したうえで、その全体像を捉え直し、歴史、理論、実践方法を1冊で知ることができる内容となっています。現在的な視点からフィールド・レコーディングを網羅的に紹介し、そのすべてが理解できる国内で初めての1冊です。
★フィールド・レコーディングより深く知るためのディスク&ブックガイド付き
★柳沢英輔×佐々木敦(思考家)×角田俊也(サウンド・アーティスト)による鼎談を収録
ブックデザイン:大田高充
カバー写真:エレナ・トゥタッチコワ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
qoop
KATSUOBUSHIMUSHI
窪
遠藤 悪