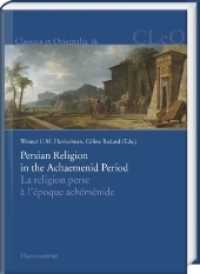内容説明
三代武家政権の誕生から崩壊までを徹底解説! 源頼朝・足利尊氏・徳川家康は、いかにして天皇政権と対峙し、幕府体制を確立させたのか? その核心に迫る! 歴史時代小説読者&大河ドラマファン、必読! 1冊で三大幕府がマスターできる、画期的な歴史新書!!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
121
鎌倉・室町・江戸の三大幕府について、性格や特色を比較した本は珍しい。朝廷と距離をとり武士を統率する政権として発足した鎌倉幕府は、社会経済の変化に対応できず崩壊した。朝廷を膝下に置いた室町幕府だが全国統治の意識が低かったため諸大名の勝手を許し、謀反と戦乱の果てに応仁の乱を招き衰亡した。両者の失敗をよく研究した家康は、諸藩の内政には干渉しない代わりに全国規模では幕府の組織と法制に従わせ平和を実現した。人治国家から法治国家への移行を模索しながら、軍人政権という基本から抜けられなかった6百年余の推移が一望できる。2023/12/10
skunk_c
59
歴史作家が鎌倉・室町・徳川の幕府政治を1冊にまとめてコンパクトに解説したもの。内容は高等学校の教科書の副読本的なものと言え、いわゆる論争的部分には大きくは踏み込まず、その歴代将軍の概要から政治のあり方、経済状態、紛争などを簡潔にまとめている。文章は上手いので読みやすいが、その分歴史のダイナミズムは感じにくい。一部筆が足りていない部分があるのと、せっかく「3大幕府」と銘打ったのだから、それぞれの特徴と本質をもっと対比した章があっても良かったのでは。基本的には入門書的。ただし江戸の刑罰の説明はかなり詳細だ。2023/10/31
よっち
31
源頼朝・足利尊氏・徳川家康は、いかにして天皇政権と対峙し、幕府体制を確立させたのか?三つの武家政権の誕生からそれぞれの組織・制度・法律の特色とその崩壊までを解説した一冊。御恩と奉公で結ばれた史上初の武家政権だった鎌倉幕府の仕組み、執権政治から得宗専制政治に至るまでの経緯、全国統治の意識は低かった室町幕府の仕組みと外交、将軍独裁と応仁の乱、全国統治しながら領国支配には介入しなかった江戸幕府の職制や人民支配のしくみ、鎖国と交通・経済・刑罰。おさらいといった感じの掘り下げでしたが、違いが比較できて良かったです。2023/11/08
LUNE MER
17
各幕府の特徴を対比的にコンパクトにまとめた良書だと思うが、いかんせん300ページほどに詰め込まれているので内容を咀嚼するのは割と大変。鎌倉幕府は「鎌倉殿の13人」で、室町幕府は先日読んだ別の新書で、江戸幕府は「大奥」(よしながふみ)で多少馴染みがあったから何となくついていけたものの、知識ゼロに近い状態で本書にアタックするよりは、復習に活用するほうが役立ちそうな印象。また、各幕府の終焉は基本的にドラマチックな盛り上がりを期待してしまうところだが、サラッと淡々と終える筆運びが少し物足りなかったかも。2023/10/22
coolflat
16
40頁。11世紀になると、各地の公田を請け負い耕作する大名田堵や土着した国司の子孫などが、国衙の許可を得て荒田や原野を開拓し、私有するようになった。彼らは開発領主と呼ばれたが、やがて土地を守り領民を支配するため武装するようになった。地方の武士の誕生である。武士は同じ土地に代々住み着き、国衙と結びついていく。そして国衙の行政を担う在庁官人になったり、国衙領を支配する郡司・郷司・保司などに任じられた。2024/05/27