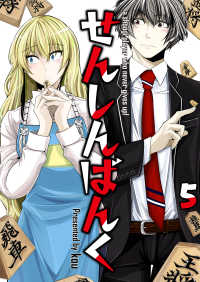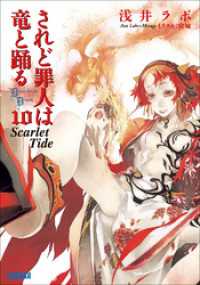内容説明
「革命」とセクシュアリティの政治思想史へ
奇跡のように安定していた徳川体制――なぜ僅か4隻の米国船渡来をきっかけに、それが崩壊し、政治・社会・文化の大激動が起こったのか。当時を生きた人々の政治や人生にかかわる考えや思い、さらにジェンダーとセクシュアリティの変動を探る。驚きに満ちた知的冒険の書。東京大学出版会創立70周年記念出版。
【本書「はしがき」より】
本書は、広い意味での政治に関する、「日本」における思想の歴史を論ずる。時期は、徳川の世から、(従来、多くの人によって「明治維新」と呼ばれてきた)大革命を経て、おおむね「明治」の年号が終わる頃までである。主題は、その間の、特に重要で、しかも現代にも示唆的だ、と筆者の考えたものである。但し、その議論の方法と主題の選定は、(筆者の主観では)往々、かなり冒険的である。
方法として特に努めたのは、日本を日本だけを見て論じない、ということである。「日本史」を、西洋や東アジアの異なる歴史をたどっている人々の側からも眺め、双方を比較し、双方に対話させようとしたのである。無論、それは、西洋や中国を基準として日本の「特殊性」をあげつらうということではない。それぞれの個性と、それにもかかわらず実在する共通性の両面を見ようというのである。日本史も、東アジア史の中で眺めるべきだとよく言われる。当然である。しかし、常にそこにとどまっている必要はない。日本史も人類史の一部である。
【主要目次】
はしがき
I 「明治維新」とはいかなる革命か
第一章 「明治維新」論と福沢諭吉
第一節 「明治維新」とは?
第二節 「尊王攘夷」
第三節 ナショナリズム
第四節 割り込み
第五節 「自由」
第二章 アレクシ・ド・トクヴィルと3つの革命――フランス(1789年~)・日本(1867年~)・中国(1911年~)
はじめに
第一節 「一人の王に服従するデモクラティックな人民」 《 Un peuple d mocratique soumis un roi 》
第二節 中国――デモクラティックな社会
第三節 デモクラティックな社会の特徴
第四節 中国の革命(1911年~)
第五節 日本の革命(1867年~)
おわりに
II 外交と道理
第三章 思想問題としての「開国」――日本の場合
はじめに
第一節 「文明人」の悩み
第二節 「日本人」の悩み
第四章 「華夷」と「武威」――「朝鮮国」と「日本国」の相互認識
はじめに
第一節 通信使の目的と「誠信」
第二節 「蛮夷」と軽蔑――朝鮮側の認識
第三節 「慕華」と「属国」――日本側の認識
第四節 破綻の要因
おわりに
III 「性」と権力
第五章 「夫婦有別」と「夫婦相和シ」
第一節 「中能」(なかよく)
第二節 「入込」(いれこみ・いれごみ・いりこみ・いりごみ)
第三節 「不熟」(ふじゅく)
第四節 「相談」(さうだん)
第五節 「護国」(ごこく)
おわりに
第六章 どんな「男」になるべきか――江戸と明治の「男性」理想像
はじめに
第一節 徳川体制
第二節 維新革命へ
第三節 明治の社会と国家
第七章 どんな「女」になれっていうの――江戸と明治の「女性」理想像
はじめに
第一節 徳川体制と「女」
第二節 「文明開化」と「女」
おわりに
IV 儒教と「文明」
第八章 「教」と陰謀――「国体」の一起源
第一節 「機軸」
第二節 「道」
第三節 「だましの手」
第四節 「文明」と「仮面」
第五節 「国民道徳」
第九章 競争と「文明」――日本の場合
第一節 「競争原理」
第二節 徳川の世
第三節 明治の代
第十章 儒教と福沢諭吉
はじめに
第一節 福沢諭吉の儒教批判
第二節 天性・天理・天道
V 対話の試み
第十一章 「聖人」は幸福か――善と幸福の関係について
第一節 問題設定への疑問
第二節 回答の必要
第三節 応報の類型
第四節 隠遁と方便
第五節 「独立自尊」
おわりに
第十二章 対話 徂徠とルソー
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
ぽん教授(非実在系)
竹の花
Hiroki Nishizumi
ウエオロ涼