内容説明
私たちの生活に欠かせない
橋や電車、水門、トンネル、道路、ダムなどの
土木構造物「ドボク」には
実はすごい技術や奥深い歴史が詰まっています。
どうしてこんなに形になったのか?
こんな大きいものをどうつくったのか?
素朴な疑問から、見どころ、
写真を撮りたくなるポイントまで
知ると世界が変わる
ちょっとマニアックな東京のドボクを巡ります!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
115
東京都内の62の土木構造物を美しいカラー写真とともに紹介する。四人の執筆者は工学者で、技術的なポイントを押さえた解説も充実している。半数以上が、終戦以前に作られた構造物。関東大震災や東京大空襲などを切り抜け、今も公共の用に供していることが凄い。関東大震災の復興で隅田川に一連の架橋を行う際、全てを同じ構造の橋にすべきとの政府やメディアからの要求を跳ね除け、多様な形式の橋梁群を採用した土木技術者の思いが、「橋の博覧会」と呼ばれる隅田川の美しさに繋がっている。昔の日本の方が、今よりずっと豊かだったかもしれない。2024/04/14
キク
65
東京の代表的土木施設を、写真と都市開発史的な位置づけの詳しい解説で紹介してくれる。ブラタモリの土木版みたいで、すごく面白かった。東京駅、渋谷駅、ゆりかもめ、東京タワー、スカイツリー、レインボーブリッジなどの超メジャー級から、地下の巨大調整湖や水道局施設などの普段なかなか見れない施設まで揃っていて読み応えがあった。建築の設計は、「美しさ」がかなり重視される。でも土木設計では、全然重視されない。大事なのは、安全性とコストになる。それでも、結果としてすごく美しい。神は細部だけじゃなくて、巨塊にも宿るんだな。2023/07/24
yyrn
28
戦争の道具に過ぎない戦車に美しさは必要ないだろうが、子ども時代はもの凄くかっこよく見えて何台もプラモデルを作っていたが、機能的に優れているモノは美しいと思える感性が人間には備わっているからではないかと、この本を読んで改めて思った。▼東京都内でみられる美しいと著者らが感じた62の土木施設(橋を中心に高架や駅や空港、タワーやトンネル、街路や公園、水門や閘門、上水やお濠、石垣まで)をエリア毎に、見た目以外でも各施設の機能面での素晴らしさを素人にも分かり易く解説してくれる本。散歩の動機付けにうってつけかw。2024/02/24
飼い猫の名はサチコ
4
街歩きが気持ちのよい季節を迎え、「鑑賞」とまではいかなくても、知識をもって街にあるインフラ施設を見たら、見え方が変わって面白いだろうと思い一読。写真満載でバーチャル散歩を楽しめた。大正2年に架けられた先代の四谷見附橋。欄干の一部を新宿歴史博物館で見たけれど、大部分は、多摩ニュータウンの長池公園に移設されて、美しく復元されているとこの本で知った。近々、現地を訪れてみたい。2024/05/06
rubidus
4
魅力的な構造物がこんなにもあるのかと思う。知識が増えると風景から読み取れる情報量、解像度が上がってくる。2023/11/22
-

- 電子書籍
- ストレスゲーム【タテスク】 第37話 …
-
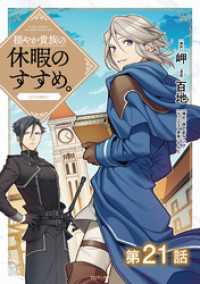
- 電子書籍
- 【単話版】穏やか貴族の休暇のすすめ。@…
-
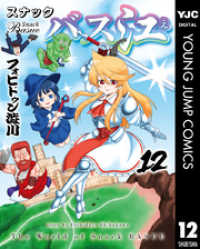
- 電子書籍
- スナックバス江 12 ヤングジャンプコ…
-
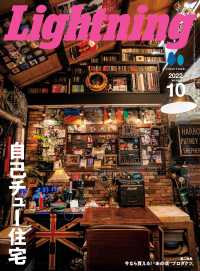
- 電子書籍
- Lightning 2022年10月号…
-
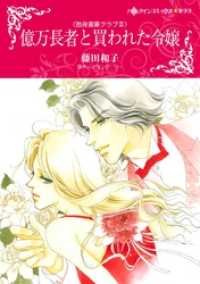
- 電子書籍
- 億万長者と買われた令嬢〈独身富豪クラブ…




