- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「自動改札機を通過するとき、腕をクロスさせなければならない」「ハサミや定規、スープをすくうレードルが扱いにくい」など、左利きならではの不便は多々存在する。さらに、かつては左利きだと結婚に差し障りが生じたことすらあったという。中国の古典『礼記』に「食事をする手は右手」と記されているため、日本では長らく左手で箸を持つのは不作法と見なされ、左手で箸を持つ女性は「親の躾がなってない」と判断されることがあったのだ。本書では左利きの苦難の歴史と現状を解説し、左利きが暮らしやすい社会を生むための取り組みも紹介。坂本龍一や石原慎太郎など左利きの著名人のエピソードも語る。 ●人類における左利きの割合――世界と日本 ●なぜ左利きが誕生するのか? ●「左利きは九年寿命が短い」説 ●儒教の教え――「食事をする手は右手」 ●日本神道の教え――「左は右よりも尊い」 ●左利きだとお嫁にいけない!? ●「左利きは右脳型」説は本当? ●左利きの才人、偉人たち ●左利きへの共感を示した米津玄師
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Kurara
52
★3 左利きに憧れたけど実は生きずらいというのは 友達にも聞いたことがあった。子供も小さい頃は左でご飯を食べていたけれどなぜか祖父母が嫌い右手で食べることも教えとうとう右利きになっていたなぁ。今の時代では左利きの方が脳の発達にはいいのでしょうね。#NetGalleyJP2023/09/19
よっち
34
左利きならではの不便は多々存在する。その苦難の歴史と現状を解説し、左利きが暮らしやすい社会を生むための取り組みも紹介しつつ著名人のエピソードも語る一冊。世界と日本における左利きの割合、そもそもなぜ左利きが誕生するのか?自動改札やハサミといった道具や設備の問題、文字や習字におけるデメリット、矯正の現実だったり、各国で左利きでどのような不利益が生じていたのか、左利きの脳と身体の関係や著名人なども紹介しつつ、サイレンスストレスを解消し、左利きにやさしい社会づくりのためには何が必要かいろいろ参考になる一冊でした。2023/09/19
みこ
22
左利きとして迷わず手に取った一冊。世間で細かく苦労している左利きあるあるを面白おかしく紹介する本と思いきやマイノリティとしての左利きに関する提言。自分がマイノリティ委に属しているという自覚がなかっただけに意外な展開だった。私自身が鋏にしろ自動改札にしろ後天的なものは特に苦労することなく右手を使っていたからかな。一瞬だけど斎藤一の名前が出てきたことに妙な満足感。2023/10/13
だのん
15
時代や宗教などで、左利きに対する対応が様々で興味深い話がたくさんありました。家族や職場などまわりに左利きの方はたくさんいるので、いろいろと考えるところがありました。左右両利きはうらやましく思いますが、当人としてはどうなのでしょうか。2024/05/31
shikada
14
左利きが受ける隠れた差別や不便、また左利きに関する統計などをまとめて、利き手のユニバーサルデザインを提案する一冊。左利きの人口割合は、諸説あるけどおおむね全体の10%。駅の改札やハサミなど、世の中の道具の多くは右利き向けに設計されていて、左利きには扱いにくい。まだ歴史的に左手は良からぬものとして扱われていて、少し前の日本でも「左ギッチョは嫁に行けない」なんて言説がまかり通っていたのには呆れる。左利きの子供を無理に右利きに矯正しようとすると、小児神経症につながるおそれがあるのは初めて知った。2023/12/09
-
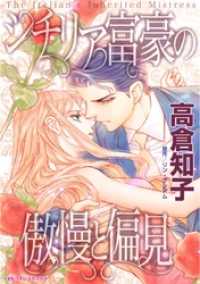
- 電子書籍
- シチリア富豪の傲慢と偏見【分冊】 3巻…




