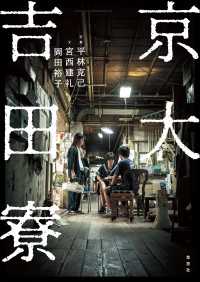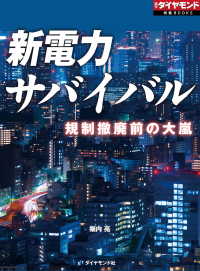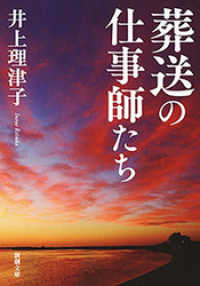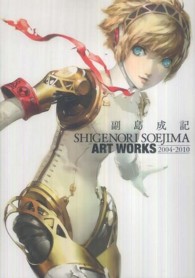内容説明
世界はどのようにして豊かになったのか?
いまだ貧困が世界中に存在するとはいえ、歴史的に見た場合、
いま生きている人の大半は200年前に生きていたどんな人間よりも裕福になった。
この「経済成長」はどうやって達成されたのだろうか?
大きな変化を生み出した産業革命は、なぜ18世紀の英国で始まったのか?
それに続いて他のヨーロッパ諸国やアメリカ、日本が発展できたのはなぜか?
そして、なぜいまだに貧しいままでいる国や地域が存在するのか?
じつは持続的な経済成長に成功した経済圏にはいくつかの前提条件があった。
その条件を、地理、政治、文化、宗教、人口動態、植民地などの要因をもとに
最新理論を引きつつ検証した、「経済成長」の謎を解くグローバルヒストリー。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
absinthe
108
著者自身も1個の原因で解明しようなどと思っていないと明言。様々な説を紹介、各説の利点と欠点を述べるという、きわめて慎重な姿勢。現在の研究の最先端はおぼろげにわかるが、その分歯切れがよいとは言えない。様々な要因が絡まって成長したりしなかったりだ。繰り返し目についたのは教育というキーワードだった。これが無いと産業革命以後の成長が望めないようだ。著者も明治以後の日本の急成長にはそれまでの教育水準の高さが関連したと考えている。2025/08/05
ふみあき
55
なぜイギリスは世界に先駆して産業革命を達成できたのか? なぜマルサス的停滞を抜け出し、現在に至るまでの持続的経済成長を実現できたのか? 行政権力に対する制度的抑制の確立や、所得水準の高さなどを始め、複数の要因がイノベーションを喚起した、というのが著者たちの結論。しかし(日本も含めた)後進国は、すでに開発されたテクノロジーを利用すればよいだけだったので、(英国とは真逆の)中国のような権威主義的な独裁国家でも経済成長できてしまう……という理解でいいのだろうか? それとも中国もいずれ民主的な体制に漸近していく?2024/04/06
ゲオルギオ・ハーン
28
経済成長の要因を地理や制度、文化、人口、植民地の要因について再考し、北西ヨーロッパが近代化が進み豊かになった理由、産業革命はイギリスではじまった理由、工業化について解説している。読み終えてみると教科書的な一冊だった印象。魅力的な小見出しでふと気になるがあまり飛躍した話にしないようにブレーキがかかりちょっと退屈なところがあった。各章のまとめも歯切れが悪くて文化の場合は他の要因との相互作用が見られるので重要な点だ、と具体性に欠く書き方で分かりにくい。2025/04/24
とある本棚
24
経済成長に関する文献をレビューする一冊。具体的には「地理」「人口」「制度」「植民地」といったテーマについて、経済史の論文を中心に過去の議論を振り返る。類書との違いは「文化」に一章が割かれていることであり、宗教と経済成長の関係についても議論されている。本書から直ちに経済成長の処方箋が得られるわけでないが、示唆に富む記述も多い。個人的にはアセモグルらが過去に論証したように、政治制度の包摂性がやはり鍵になるのだと強く感じた。2024/01/03
かずい
11
読み応えのある本で、何度か読まないと全体を把握できない。世界の歴史上の経済成長した国を「地理、制度、文化、人口、植民地」から考察。人類の歴史で見るとイギリスの「産業革命」のパワーは経済成長に多大な影響を及ぼした。それには資本と熟練工の存在で、新しい発明や商品開発などが生まれた。ウェイバーの「プロテスタンティズム~資本主義の精神」の話も出てくるが、著者はウェイバーの説を否定するが、プロテスタントによる資本と技術屋の発生は産業革命の礎になったのではないかと思った。2024/03/01