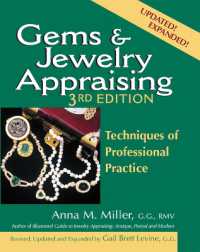- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「朝起きられない」「日中はだるくて体が動かない」という主訴を持つ起立性調節障害。中高生の1割、小児科受診の中学生では2割を占め、不登校の大きな原因だ。的確な診断ができる医師も多くなく、「怠け病」と言われる患者も多い。小児科医・スポーツドクターである著者は、起立性調節障害を栄養の観点から分析、治療・改善させている。本書では青年期までの発達に必要な栄養や、運動との関係、周囲の対応を症例を交え解説する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
haruka
20
朝、起きられない、朝に弱いーーこれは身体疾患で、中高生の1割がこれにあたる。 タンパク質や鉄の不足が一因だと。 でもこれって、朝つらいから食べられないだけでは? それより朝型社会に原因がある気がしてならない。 とくに中高生の体内時計は、性ホルモンの変動によって夜型方向へ数年間シフトするのだ。 これはスマホのせいではなく生物としてそうなる。 そんな彼らに朝6時台に起きて早寝しろだなんて無理な話なのだ。 大人の夜型人間もそう。私はいまだに7時半に起きる生活がつらい。2025/11/07
カイエ
9
息子の寝起きが悪いので読んでみた。タンパク質とミネラルの不足、それから炭水化物過多。当てはまるなぁ。朝摂取したタンパク質は日中セロトニンを作り、夜にはメラトニンになる。つまりは朝食が睡眠の質に関係するということ。起立性調節障害の治療だけでなく、予防や体質改善にも有益な本だと思いました。2024/01/19
Asakura Arata
5
100年前にすでに糖尿病の治療法として低糖質ダイエットがあったというのは驚き。そういえば、森田正馬の原著にも傷口は無闇に消毒するなみたいな話があったよな。これらの事実を鑑みるに、医療は全面的に進歩しているわけではなさそうだ。プロテインと鉄分の摂取を強調するところは藤川先生と共通している。発達障害児に低フェリチンが多いというのは興味深い。2023/12/18
Iwata Kentaro
5
要素還元主義は(極端な場合を除けば)たいてい間違いだ。2023/09/15
やなぎ
4
起立性調節障害は「発達障害」というイメージだったが、病気なのか?栄養の調整で治癒したり改善したりするのであれば救われる人は多いだろう。まだまだわからないことが多いな。2024/11/06