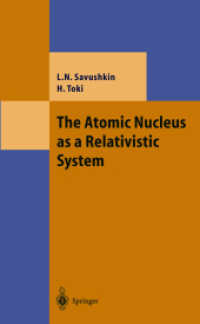内容説明
かつて日本古代史は、『日本書紀』『古事記』や中国の史書に頼らざるを得なかった。だが一九九〇年代後半以降、三万点以上に及ぶ飛鳥時代の木簡の出土が相次ぎ、新たな解明が進み始める。本書は、大化改新、中国・朝鮮半島との関係、藤原京造営、そして律令制の成立時期など、日本最古の木簡から新たに浮かび上がった史実、「郡評論争」など文献史料をめぐる議論の決着など、木簡解読によって書き替えられた歴史を描く。第2回古代歴史文化賞大賞受賞作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shoji
69
木簡は嘘偽りのない極めて信憑性の高い史料である。古代人のメモ書であり、用済みになれば捨てられる。それに対して、正史と言われる日本書紀や続日本紀は政治色に満ちて編纂された可能性があり、高等な史料批判から始めねばならない。常識と言えば常識だが、改めて木簡の意義を認識した。ちなみに、用を足した後、使わなくなった木簡をヘラの様に使ってお尻を拭いたとか。その名もクソベラ。古代研究とはなんとも奥深いことよ。2017/11/21
南北
58
木簡とは文字の書かれた木片のことだが、日本の木簡は38万点あり、日本古代史に新たな光を当てるものと言える。特に日本書紀では「国-郡-里など」となっている行政区域が木簡では700年まで「国-評-五十戸」と記載されていることがわかり、いわゆる「郡評論争」を決着させることになった点は興味深く読むことができた。大化の改新の「改新の詔」でも「国-郡-里」の表記となっていて、今後はなぜ日本書紀が資料の書き換えを行ったのかを解明する必要が出てくることになろう。考古学の発掘資料が大きな影響を与えることがわかる好著。2024/01/12
月をみるもの
16
この本で扱われている木簡の多くは、飛鳥のみならず藤原京(ほとんどは橿原市)から出土している。出土した木簡上の文字を読む時、そこで考古学と文献史学が出会う。どちらかだけでは決してわからないことが、両者の融合によって解き明かされる。2019/10/15
take5
13
内容は書名通りで、1990年代後半以降の発掘調査(著者が携わったものも)により飛鳥と藤原京跡から大量に木簡が出土したそうで(2011年現在で4万5千点)、それ以前に発掘された木簡も含めた、飛鳥時代の木簡について一般読者にも分かりやすく解説されている良書です(文字表記(一部写真付き)と共に各種木簡が紹介されていて、その当時の役人や工人の姿が垣間見え、飛鳥時代や『万葉集』に興味のある私にとっては読みどころ満載でした(付箋紙100箇所くらい貼ってしまった^^;本屋などで口絵3の「役人の顔を画いた墨画」だけでも2019/10/01
はちめ
11
木簡の発掘により様々な知見が得られていることは知っていたが、まとまった本を読んだのは初めて。木簡は誤字を除けば真実を伝える一次資料だけに、上手に読みとけば当時の社会の実態に迫れるということが良く分かる。本書は2012年の出版だが、その後も木簡の発掘は続いていると思うので、続編も期待したい。☆☆☆☆2020/08/08
-
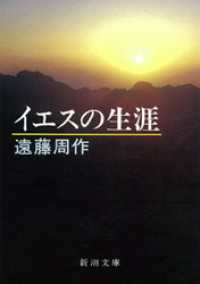
- 電子書籍
- イエスの生涯