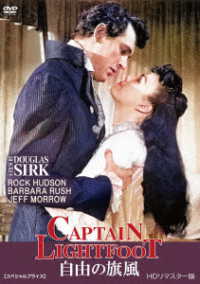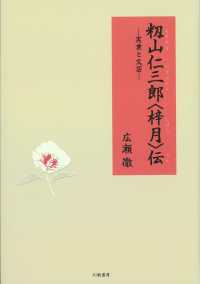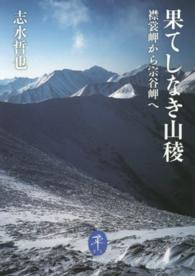内容説明
私たちにとって、墓とは何か?
時の権力や死生観、土地や風土に根ざした文化によって、日本ではじつに多様な葬送文化が育まれてきた。
だが、過疎化や高齢化により、今その文化が風前の灯となっている。
土葬の現在から、肉体と魂を分けて埋葬する「両墓制」、沖縄の風葬やアイヌの男女別葬、無数の遺骨を粉末状にして固めた「骨仏(こつぼとけ)」まで――。
全国各地を歩いて取材した僧侶が、知られざる弔いのかたちを写真とともに明らかにしながら、
日本人がいかにして死と向き合ってきたかを問いなおす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
98
著者が住職だから、無縁仏や墓じまいなどの現実的な話題かと思いきや、弔いの歴史や地域的特徴など墓についての体系的な説明に、自分の無知を思い知る:両墓制の意味、殯の意味、明治の火葬禁止令、土葬は法律で禁止されてないこと、日本は火葬大国(欧米との違い)、火葬禁止の在日ムスリムの土葬墓の課題、天皇家は泉涌寺の檀家だった、沖縄のユタ・ノロ・洗骨、男女別葬のアイヌなど…。令和になり天皇が土葬から火葬に変わるように、墓を取り巻く社会の変化は著しい。地方の墓じまいと都会の永代供養(納骨施設)という今日的課題も理解できた。2023/11/13
ネギっ子gen
66
【伝統的な土葬や両墓制の現在から、沖縄の風葬やアイヌの男女別葬、骨仏など】各地に残る不思議な形態の墓や埋葬を取材してきた僧侶が、知られざる弔いの形を写真とともに明らかにしながら、日本人がいかにして死と向き合ってきたかを問い直した新書。<「墓は、「負の歴史」を教えてくれるだけではない。地域の歴史や習俗などを知る「生きた教材」でもある。ところが、日本各地に残された墓制が、間もなく消滅してしまう危機に瀕している。/滅びゆく墓制から、地域や日本人の弔いの歴史、さらには習俗を知ってもらうのが本書のねらいだ>と。⇒2023/10/03
ヒデキ
58
個人的な話ですが、お墓や宗教に興味を持ちだしたのは、 旦那寺の役員をしてからです 「なんで、みんなでこんな組織を維持するのを頑張っているんだろう」と思ったからでした。 鵜飼さんの話も組織的な同行がある前提で描かれている感じがしていますが、他所に出ている人間が、ここへ入るのは、 結構、力がいるなあと思っていたことを思い出しながら読んでいました。 最近、墓所(サンマイ)に参って思うのは、地域から出ていかれた方のお子さんは、ここにお墓があることをご存じかな?と思うことです2023/12/17
よっち
32
私たちにとって墓とは何か?全国各地を歩いて取材した僧侶が、知られざる弔いの形を写真とともに明らかにしながら、日本人がいかにして死と向き合ってきたか問いなおす一冊。縄文時代の貝塚から弥生時代の古墳、中世の石仏や供養塔、江戸時代の檀家制度や庶民の墓、土葬や遺体と魂を別々に弔う両墓制の現在。有名武将や徳川将軍家の墓所、アイヌや沖縄、企業墓といった文化にも触れつつ、最近になって検体墓や樹木葬、海洋散骨、手元供養といった選択肢が出てきた現状は、弔いをしたくてもできない人が増えていることと無関係ではないんでしょうね。2023/09/26
miel
24
日本の葬送文化についてまとめられた本作の著者はご住職だそう。歴史から由来、地域独自の慣習など、明解で読みやすいのが良かった。古墳から土葬、火葬墓、永代供養のロッカー式納骨堂、樹木葬、各種散骨辺りまでは自分の拙い知識でもわかる範囲だったからサラサラと読んでいたけれど、最終章が面白かった。企業墓、献体墓、墓じまいをはじめとした最新お墓事情については目からウロコの連続。アメリカのコンポスト葬、良いな。確かに現代式土葬のようと言えば、そうかもしれない。土に還る土葬って一周回って新しい葬儀の形になる日が来るのかも。2023/10/06
-

- 電子書籍
- レベルドレイン -絶対無双の冒険者-【…