内容説明
十字軍と言えば、もっぱら運動としての面が注目され、十字軍士たちが各地に建設した諸国家、すなわち十字軍国家の全体像が語られることはなかった。だが、1098年のエデッサ伯国建国から、1798年のナポレオンによるマルタ島攻撃までの実に700年にもわたり十字軍国家は存続していた。ローマ教会、ビザンツ帝国、神聖ローマ皇帝、イスラーム勢力や地中海の諸商業都市、傭兵団、さらには来襲するモンゴル勢など、多種多様な勢力が複雑に絡み合う興亡の歴史を、第一人者が活写する。 【目次】序 十字軍国家とは何か/I ラテン・シリア/第1章 ラテン・シリアの誕生(1097-1099年)/第2章 ラテン・シリアの形成(1098-1118年)/第3章 ラテン・シリアの成長(1118-1146年)/第4章 ラテン・シリアの発展と分断(1146-1192年)/第5章 ラテン・シリアの回復と再分断(1192-1243年)/第6章 ラテン・シリアの混乱と滅亡(1243-1291年)/II キプロス王国/第7章 キプロス王国の形成と発展(1191-1369年)/第8章 キプロス王国の混乱と消滅(1369-1489年)/補章1 ヴェネツィア領キプロス(1489-1573年)/補章2 キリキアのアルメニア王国(1198-1375年)/III ラテン・ギリシア/第9章 ラテン帝国(1204-1261年)/第10章 フランク人支配下のモレア(1)(1204-1311年)/第11章 フランク人支配下のモレア(2)(1311-1460年)/補章3 カタルーニャ傭兵団とアッチャイオーリ家(1311-1462年)/IV 騎士修道会国家/第12章 ドイツ騎士修道会国家(1225-1561年)/第13章 ロドス期の聖ヨハネ修道会国家(1310-1523年)/第14章 マルタ期の聖ヨハネ修道会国家(1523-1798年)/あとがき/主要参考文献/十字軍国家支配者一覧
目次
序 十字軍国家とは何か/「十字軍」の定義/十字軍士と十字軍特権/永続的十字軍特権と十字軍の終焉/十字軍国家の定義と本書の構成/I ラテン・シリア/第1章 ラテン・シリアの誕生(1097─1099年)/アルメニア人の居住地域へ/ボードゥアン・ド・ブーローニュとタンクレーディの対立/エデッサ伯国の成立/アンティオキア占領/アンティオキア侯国の誕生/エルサレムの征服/第2章 ラテン・シリアの形成(1098─1118年)/アンティオキア侯ボエモンド一世の苦悩/ゴドフロワによる教会国家の建設/ボードゥアン一世のクーデター/沿岸部の制圧/アンティオキア侯国の摂政タンクレーディ/ボエモンド一世の末路/エデッサ伯ボードゥアン二世の復活/トリポリ伯国の誕生/マウドゥードの侵攻/「血の平原の戦い」/ボードゥアン一世の死/第3章 ラテン・シリアの成長(1118─1146年)/ボードゥアン二世のクーデター/ラテン・シリアの宗主として/ボードゥアン二世の捕囚/ティール占領/ボードゥアン二世の帰還/ザンギーの登場/ラテン・シリアの君主たちの死/アンティオキア侯国の内紛/ザンギーの帰還/ビザンツ帝国の侵攻/エデッサ伯国の滅亡/第4章 ラテン・シリアの発展と分断(1146─1192年)/ダマスクスを巡る攻防/エデッサ伯国の完全消滅/エルサレム王国の内戦/アスカロンの占領/(第一次)ヤコブの浅瀬の戦い/キプロス侵攻/ビザンツ帝国との関係修復/ボードゥアン三世の死とアモーリーの即位/エジプト遠征へ/サラーフッディーンによるエジプト制圧/アモーリーとヌールッディーンの死/ボードゥアン四世の即位/ボードゥアン四世とサラーフッディーンの衝突/王党派とバロン派の対立の顕在化/ギー・ド・リュジニャンの即位/ハッティーンの戦い/エルサレムの陥落/命拾いしたラテン・シリア/第5章 ラテン・シリアの回復と再分断(1192─1243年)/アンリ・ド・シャンパーニュの「即位」/ボエモンド三世とレヴォン二世の対立/二つの王国の誕生とアンリの死/エメリー・ド・リュジニャンの統治/アンティオキア侯位継承戦/ジャン・ド・ブリエンヌの即位/レヴォンの勝利/第五回十字軍とボエモンド四世の復権/ボエモンド四世の報復/エルサレム国王フリードリヒ二世/ヤッファ協定/ロンバルディア戦争の勃発/二つの十字軍/ロンバルディア戦争の終結とラテン・シリアの再分断/第6章 ラテン・シリアの混乱と滅亡(1243─1291年)/エルサレムの再喪失/ラ・フォルビーの戦い/ボエモンド五世の苦悩/ルイ九世の下での安定/聖サバス戦争の始まり/アイン・ジャールートの戦い/バイバルスの猛攻/聖サバス戦争の再燃/エドワード王太子の十字軍/ユーグ三世の失策/シャルル一世・ダンジューのエルサレム国王位購入/トリポリ内戦/キプロス国王の復権/トリポリ伯国の滅亡/アッコンの陥落/II キプロス王国/第7章 キプロス王国の形成と発展(1191─1369年)/キプロス島の制圧/ギー・ド・リュジニャンによる島の再建/キプロス王国の成立/ロンバルディア戦争とキプロス王国の独立/二人のユーグの争い/産業と農民/教会/シャルル一世・ダンジューとの闘争とエルサレム王国の滅亡/アモーリー・ド・リュジニャンのクーデター/経済的復興/ピエール一世と永続的十字軍特権/ピエール一世の暗殺と十字軍熱の冷却/ピエール一世のもう一つのもくろみ/第8章 キプロス王国の混乱と消滅(1369─1489年)/報復の融合/ジェノヴァ軍のキプロス侵攻/キプロス国王ジャック一世/マムルーク朝の属国に/家庭問題/「キプロス人」の形成/シャルロット対ジャック/キプロス国王ジャック二世の結婚/ヴェネツィアへの譲渡/補章1 ヴェネツィア領キプロス(1489─1573年)/統治構造/植民地化と暴動/宗主国マムルーク朝との関係/宗主国マムルーク朝の滅亡/第三次オスマン・ヴェネツィア戦争とキプロスの防衛強化/一五七〇年の攻防/ヴェネツィア領キプロスの消滅/「キプロス国王」のその後/補章2 キリキアのアルメニア王国(1198─1375年)/アルメニア人のキリキアへの移動/ルーベン家の苦境/トロス二世の巻き返し/ムレーの謀反/兄ルーベン三世と弟レヴォン二世/アルメニア王国の誕生/アルメニア国王レヴォン一世/モンゴル皇帝の家臣に/バイバルスの脅威/キプロス王国との関係強化/瀕死のアルメニア王国/三人の国王の殺害/アルメニア王国の滅亡/III ラテン・ギリシア/第9章 ラテン帝国(1204─1261年)/ラテン帝国の成立/ヴェネツィア領ギリシア/教会組織の整備/ビザンツ系国家/トラキアの反乱とアドリアノープルの戦い/アンリ一世の即位/テサロニキの反乱/アンリ一世の死/ピエール・ド・クルトネーの即位/ロベール・ド・クルトネーの時代とテサロニキ王国の滅亡/イヴァン二世・アセンの野望とジャン・ド・ブリエンヌ/ボードゥアン二世・ド・クルトネーのヨーロッパ遊説/モンゴルの脅威と二度目のボードゥアン渡欧/ニカイア帝国の勢力拡大/ラテン帝国の滅亡/第10章 フランク人支配下のモレア(1)(1204─1311年)/ペロポネソス半島の制圧とアカイア(モレア)侯国の誕生/その他の諸侯領/ジョフロワ一世とオトン一世/安定期の到来/内紛とペラゴニアの戦い/アカイア侯国の内部状況/司教区/第二局面の入り口/ヴィテルボ協約/アルバニアを巡る攻防/フローラン・ド・エノーの統治期/フィリップ・ド・サヴォワの廃位/ナポリ国王の直轄地として/カタルーニャ傭兵団の侵攻/第11章 フランク人支配下のモレア(2)(1311─1460年)/ルイ・ド・ブルゴーニュとフェラン・デ・マヨルカ/マオー・ド・エノーの運命/アンジュー家離れ/アッチャイオーリ家の登場/カトリーヌ・ド・ヴァロワのもたらした分断/オスマン朝の脅威/アッチャイオーリ家の台頭/ロベール・ド・ターラントの死と内紛/聖ヨハネ修道会への貸与とナバラ傭兵団の登場/聖ヨハネ修道会による購入/アメデー・ド・サヴォワの介入/ネリオ一世・アッチャイオーリの死/アカイア侯ペドロ・ボルド・デ・サンスペラーノの誕生/ビザンツ帝国の勢力拡大/最終局面/補章3 カタルーニャ傭兵団とアッチャイオーリ家(1311─1462年)/カタルーニャ傭兵団によるアテネ公国占領/対カタルーニャ傭兵団の十字軍/ネオパトラス公国建国/ゴーティエ六世・ド・ブリエンヌの復権の試み/ドン・アルフォンソの息子たち/アテネ兼ネオパトラス公位および総代理人職の推移/ロヘル・デ・ルリアの謀反/カタルーニャ傭兵団の内部分裂/テーベの占領/アテネとネオパトラスの占拠/アテネ兼ネオパトラス公ネリオ一世・アッチャイオーリ/ヴェネツィア領アテネ公国/アントニオ・アッチャイオーリの公位簒奪/アテネ公国の終焉/IV 騎士修道会国家/第12章 ドイツ騎士修道会国家(1225─1561年)/ヴェンド十字軍からリヴォニア十字軍へ/プロイセンへのドイツ騎士修道会の導入/リヴォニア帯剣騎士修道会の編入/一二六〇年の大反乱と入植活動/マリエンブルクへの本部移転/タンネンベルクの戦い/一三年戦争/ドイツ騎士修道会領プロイセンの消滅/騎士修道会のその後/第13章 ロドス期の聖ヨハネ修道会国家(1310─1523年)/ロドス島の獲得/基盤形成の模索/交易活動の開始と教皇庁の介入/大シスマの影響と「言語」による分裂/マムルーク朝との良好な関係/総長ジャン・ド・ラスティクの改革/第一次ロドス包囲戦/ジェムの亡命/マムルーク朝の滅亡/ロドス陥落/第14章 マルタ期の聖ヨハネ修道会国家(1523─1798年)/宗教改革と聖ヨハネ修道会/マルタ包囲戦/レパントの海戦/私掠船の活用/国際的な国家間協定と私掠活動の抑制/フランス革命の影響/ナポレオンによるマルタ占領と十字軍の終焉/その後の聖ヨハネ修道会/あとがき/主要参考文献/十字軍国家支配者一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
MUNEKAZ
kuroma831
スプリント
じょあん
-

- 電子書籍
- いつか子供がほしいと思っているあなたへ
-
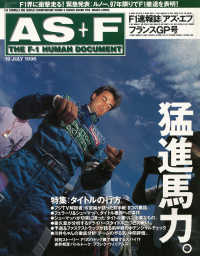
- 電子書籍
- AS+F(アズエフ)1996 Rd09…
-

- 電子書籍
- 桜色キスホリック 分冊版(12)
-
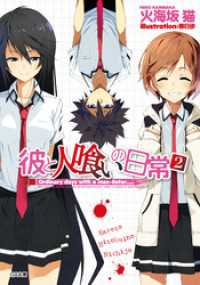
- 電子書籍
- 彼と人喰いの日常2 GA文庫
-
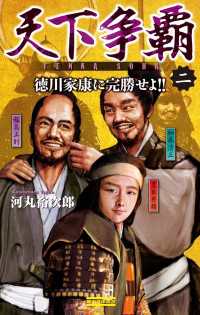
- 電子書籍
- 天下争覇2 - 徳川家康に完勝せよ!!…




