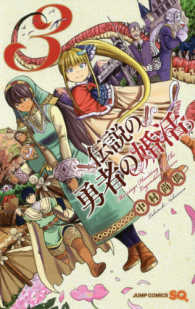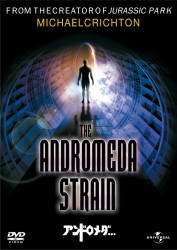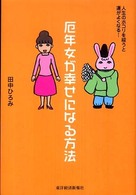内容説明
病的なまでに音楽に作曲家の自己のほとばしりを聴き取ろうとする「ベートーヴェン症候群」。19世紀以来、聴取に大きな影響を及ぼしてきたこの病の実態を解き明かす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
100
「音楽解釈」には3段階の歴史がある。当初は、客観的な「修辞学」。19世紀に、音楽を作曲家の人生の主観的表現として捉える「解釈学」の枠組みに変わり(著者はこれを「ベートーヴェン症候群」と定義する)、20世紀に、芸術は技巧であるとするモダニズム美学により、再び客観性に回帰する風潮が高まったと言う。現在も、多くの楽曲解説が、ベートーヴェン症候群に毒された人たちによって、作曲者の生涯や作品の背景を踏まえた主観的解釈でなされているのを目にするが、楽理的な技術的側面を蔑ろにして情緒的に音楽を語る姿勢を、私は好まない。2022/11/08
どら猫さとっち
5
ベートーヴェンは、何故後世の作曲家たちに、大きな影響を受けたのか。その理由のひとつが、本書にあると言えるだろう。ベートーヴェンの音楽を、自伝として聴くと、その作品を手がけた想いや背景が浮かんでくるのが興味深い。その後の作曲家たちのことも書いてある。ベートーヴェンはロマン派音楽の先駆けというより、現代音楽の世界を垣間見た音楽家ではないだろうか。2022/10/08
小鳥遊 和
3
trazom氏の優れた要約に感謝。補足の意味で第二章冒頭を要約する。ベートーヴェンが生きたのは音楽表現が客観的構築物とみなされた時代だが、同時代には詩人たちが表現の主観性という理念を表明し始めていた。ベートーヴェンの音楽にも主観的性質があり、当時の人々はその新奇さを称えながらも不可解だと嘆いた。彼の死後、人々は音楽は主観的構築物だとの新しい見方から、作品を内的自己のほとばしりとして聴くようになった。今日の私たちは彼の音楽のうち、同時代の人々がもっとも理解しにくかった性質に対して最大の賛辞を寄せている。2023/07/02
takao
2
ふむ2022/12/28
Go Extreme
1
器楽による自己 客観的表現のパラダイム 修辞学の枠組: 表現は説得手段 作曲家は役者 ミメーシス 主観的表現の受容へ: 芸術は自己を覗く窓 情念という特権 抒情詩 作品のうちに作曲家を聴く: ファンタジー フモールとイロニー 客観性の時代におけるベートーヴェンの主観性 主観的表現のパラダイム 解釈学の枠組み: 誠実さを聴く 予言を聴く 一人称のベートーヴェン: 修辞学から解釈学へ 伝記 アフター・ベートーヴェン: 形式 vs. 内容 主観性は過去へも影響 客観性の回帰: 作曲家はカメレオン・霊媒師・技術者2022/05/08