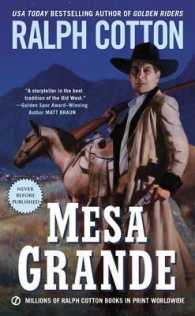内容説明
なぜ、小説を書くのか?
書き続けるために本当に大切なこととは?
そもそも、小説とは何なのか、何ができるのか――?
常に現代文学の最前線を疾走し続けた作家が、これからの創作者に向けて伝える窮極のエッセンス。
単著未収録のロングトークを中心に、文体論、作家の個性、絵画・美術といった他ジャンルとの比較など、長年にわたり発表してきた小説論を初めて精選。
さらに巻末には、著者最晩年(2005)における保坂和志氏との伝説的対談「小説の自由」を収録。
本書を読み終えた時、あなたの小説観は確実に何かが変わっている――。
(文庫オリジナル/解説=保坂和志)
【目次】
Ⅰ 小説の文体(一つのセンテンスと次のセンテンス/『考え方』の藤森良蔵/わが精神の姿勢)
Ⅱ 小説の新しさ(肉体と精神/日本文学とユーモア/私の小説作法/モデルとプライバシイ/抽象主義の作家たち/共通の心の場とは何か/摩擦音の如きグロテスク/私の考える「新しさ」ということ)
Ⅲ 小説の論理(思想と表現/愚劣さについて)
Ⅳ 小説と絵画(ゴッホの絵について/エドガー・ドガ/喜怒なきマスクの如く)
Ⅴ 小説と芝居(小説と戯曲の間/小説と演劇/初めて戯曲を書いて)
Ⅵ 小説と書簡(小説とは何か)
Ⅶ トークより(私の小説・評論・芝居(1972)/我々と文学(1972)/カフカをめぐって(1983)/いかに宇野浩二が語ったかを私が語る(1985)/男の領域と女の領域のせめぎあい(1985)/そして小説は生き延びる(2000)/対談・小説の自由(2005))
解説 保坂和志
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bartleby
フリウリ
午後
袖崎いたる
二木弓いうる@作家の赤ちゃん
-

- 和書
- 映画をつくる (新装版)