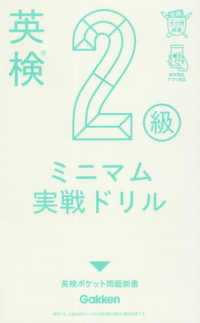内容説明
まちを観察すれば、未来のすがたが見えてくる――まち歩きを楽しみ、まちの歴史と現在を知り、まちづくりのヒントを探す多彩な視点を紹介。
都市(まち)には人々が集まり、モノやコトが溢れている。目の前の風景をただ眺めるだけでなく、「観察」という行為に高めると、まち歩きは発見に満ち、ビジネスやまちづくりのヒントまで見えてくる。まちを観察する現代の手法を紹介し、東京各エリアを中心に、歩き、カメラに収め、統計的な観察を行った。目まぐるしく変化し続けるまちの活動の断片を記録した、新世紀の考現学。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キク
61
「表参道・丸の内・自由が丘で日傘をさす人の年代・素材・色」「銀座・NYでの建物ファサードの様式・素材・広告」「1925年銀座の男女衣装の和洋割合・女性のスカートの丈」「自由が丘の外国語看板の言語・商売種類」「表参道と竹下通りのショップ商品プライス」「新宿・渋谷のラブホ街の歴史的編成」などの調査を行っている。東京都市大教授二人が学生も巻き込み人海戦術でやっていて、内容もかなり濃い。ただ、まあ、街って本で読むものじゃなくて、自分で歩くものだなと感じた。寺山修司も「書を捨てよ町へ出よう」っていってたしね2023/09/13
センケイ (線形)
11
建物や音、衣装など、かなり幅広い方法でトレンドを捉えられることに驚かされる。また、カフェの門構えや痛バなど、オタクとして楽しめるトピックも数多くある。個人的に最も奥ゆかしく感じたトピックは「自由が丘 モンブランのあるお店」(pp. 182 - 183) だ。多くの観点を得て、街を歩くのがますます楽しくなりそうである。強いて不満を言えば、2 ページひとセットのためあまり長い考察が読めないところか。しかしその分図やチャートの種類が相当多いといえる。2024/02/29
与太
1
考古学ならぬ考現学という学問を初めて知った。調査や分析方法を学ぶというより、学問の歴史をたどったり、現代の事例とその調査テーマを色々と取り合げて紹介し、様々な観点を教えてくれる入門書2024/06/16
お抹茶
1
街角で通行人や店を観察する考現学。自由が丘を筆頭に,ほとんどが東京都区内の街路を対象とする。行き交う人の服装はもとより,店の扉が開閉式なのかどうかなどとにかくいろいろなものを観察する。一つの事例につき,見開きの右側に解説,左側に地図や模式図を記す。大学のレポートでの題材集めとしても参考になる。ただし,事例が多い一方で,一つ一つの考察は深くない。こういうフィールドワークでは,定点観察することにより,本人達も意識していない社会の僅かな流れをキャッチできると思う。2023/09/25
コバ
0
学生の研究や研修などのトピックを通じて、街の観察から得られる知見を紹介している。対象となる街に偏りはあるし、数が多い分ひとつひとつはそこまで深くないが、街を観察する上でいろいろな視点があることに気付かされる。2025/10/13
-

- 電子書籍
- 0歳児スタートダッシュ物語 【フルカラ…
-
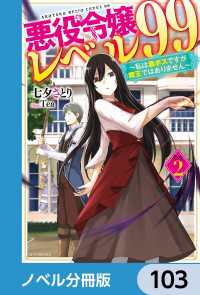
- 電子書籍
- 悪役令嬢レベル99【ノベル分冊版】 1…
-

- 電子書籍
- 織部姉妹のいろいろ【分冊版(9)】 L…
-

- 電子書籍
- 枯れ恋リハビリ~悪あがき、シてもいいで…