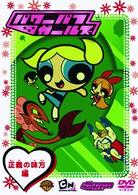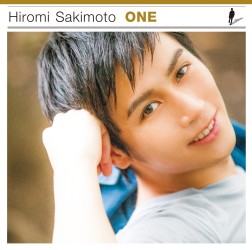- ホーム
- > 電子書籍
- > 趣味・生活(スポーツ/アウトドア)
内容説明
NHKディレクターが「猟師」になるまで。
関野吉晴氏(探検家・医師)推薦!
「ヒグマ撮りからヒグマ獲りになった著者の、命に向き合う姿勢の変化が真摯に描かれている。何よりも、狩猟現場の描写が臨場感溢れていて、惹きつけられた」
物語は、NHK自然番組ディレクターだった著者がカナダの先住民を訪ねるところから始まる。トーテムポール彫刻家であり、ハンターでもあるタギッシュ/クリンギット族の“師”と知り合った著者は、狩猟を通じて野生動物の美しさとその犠牲の上に生きることの意味を学んでゆく。
「泣くな。行きすぎた悲しみは、我が身を捧げてくれた獲物に対し、失礼だ」
「獲物に最後の力が残されていたら、彼らが死を受け入れるための時間を穢してはならない」
「彼らの再生のために祈りを捧げよ」
さらに、新たな赴任地となった北海道で、一人銃を担いで山に入る「単独忍び猟」に挑みながら、野生動物たちの生態を知り、技術を磨いてゆく。そして猟期5年目、ついに「山の王者」ヒグマを仕留める。しかしそこには、思いもかけない「置き手紙」が残されていた――。
スーパーでパックされた肉を食べることが当たり前になった現代。人間がこれからも地球で生き続けるための知恵=先住民の思想と生き方に魅せられた著者が、NHKを退職して「猟師」になるまでの軌跡を綴る“生命密着ドキュメント”。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
105
著者は元NHKのディレクター。狩猟に興味を持ち北米先住民に狩猟について共に山に入って様々なことを学ぶ。この本を読みかける時、ある県で捕獲された親子三匹のツキノワグマを駆除したことに対して多くの非難がきたというニュース。そのことを思い出しながら読んだ。文章はそっしりとした文体。哲学だと感じた。狩猟に対する狩猟を行う者の気持ち、ニュースと同じように親子のヒグマを撃ったときのこと、子供を身ごもったメス鹿のの子宮から胎児を取り出し母鹿の頭と一緒に埋めたこと。野生の動物と対峙したとき、勝ったときの相手への敬意。 2023/10/07
けんとまん1007
52
食べ物をいただくこと。目の前に、その姿がないことからくるものを考える。動物、植物(野菜・穀物・果実など)を問わず、自分自身が、どれだけ知っているか、関わっているか。以前は稲作もやっていたし、今は、家庭菜園ではあるが、それなりに作っている。しかし、動物は一切、直接的ではない。知識としてはあるが、体感しているわけではない。それらを踏まえ、命をいただくとは、その背景にあることを考える。自分も自然・大地・水の一部であることを考える。2024/01/20
あじ
23
神聖で尊い場面が続き、心が揺さぶられた。濁りゆく動物たちの瞳が最期に焼き付けるのは、敬意を捧げる筆者の姿。疲労困憊の渦中にあっても礼節を重んじ、完全なる食肉になるまで筆者は精魂を尽くす。筆力がなせる文言が数多あり、猟師になるまでの道のりを仔細に感じ取ることができた。良書である。◆併せて読むなら【いのちの食べ方】森達也/著、【猟師の肉は腐らない】小泉武夫/著2024/07/20
モーモー
19
狩猟と先住民の伝えから学ぶいのち。狩りをして、たべることよりいきさせてもらうことに感謝する!非常に学ぶべきことが多かった。 採れるだけとる、資本主義では当たり前たが、少し前は必要な分だけを山、海から恵んでもらっていた。 無駄になる前に必要な分だけ、現代人に必要な考えである2024/01/16
taku
19
狩猟にさほど興味はなかったがグッと引き込まれた。ユーコンでの暮らし、ネイティブアメリカンや日本のハンターとの交流、北海道での鹿猟から熊撃ち。命と対峙し敬意をもって獲り食らう著者の姿勢は、猟を知らない自分にもわからせてくれるものがある。ただ、繰り返されると疑念も浮かぶ。獲物に感謝し、ときには思いを巡らせ涙を流す。人間特有の精神は命との真摯な向き合いなのか、それとも自己陶酔でしかないのか。同行できたら少しはわかるだろうか。読む価値はあったが、スッキリしないものは残る。2023/10/31
-
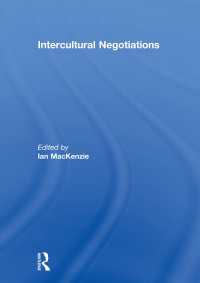
- 洋書電子書籍
-
異文化間交渉
Intercult…
-

- DVD
- 男子高校生の日常 DVD-BOX