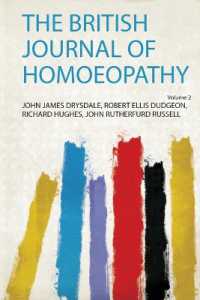内容説明
メディアの近未来を予測するとき、ラジオの歴史から学ぶことは多い。20世紀が幕を開けた頃、電波を用いたコミュニケーション領域=無線は、最新のニュー・メディアだった。そこから徐々にラジオ放送が産業として編成され、マス・メディアとして確立し、日々絶え間なく放送される番組が人々の生活文化を形成していくことになる。本書は20世紀初頭から半ばまでのアメリカにおけるラジオの動向を通じ、メディアが経験した地殻変動や、近代社会における文化の諸相に迫る。インターネット登場前夜に書かれた名著に、新章を増補した待望の文庫版。
目次
序章 メディア史の構図/メディアの地殻変動/ラジオ放送の誕生の場へ/テクノロジー・メディア・社会/本書の構成/第I章 無線想像力と産業的編制/1 夢としてのテレ・コミュニケーション/声のテクノロジー/視話法とテレフォン/プレジャー・テレフォン/エレクトリック・メディアの時代/2 エーテルを渡る声/電気の時代とエーテルの理論/ラジオの発明家たち/無線想像力と「ラジオ・ミュージック・ボックス」/3 ビッグビジネスとナショナリズム/ラジオ無線と第一次世界大戦/国有化構想とRCAの設立/RCAと相互特許協定の成立/消費財産業の発達/第II章 ラジオをめぐる心象/1 KDKA──無線から放送へ/フランク・コンラッドと仲間たち/販売促進媒体としてのラジオ/大衆=リスナーの発見/放送への対応/2 ガレージからリビングへ/ラジオへの憧憬と神秘感/ガレージからリビングへ/マニアからマス(大衆)へ/3 マス・メディアのジャズ・エイジ/繁栄のバンドワゴン/大量生産・大量消費の時代/マス・メディアが造成する情報環境/4 ラジオ・ブーム!/ラジオ、家電となる/家具を装うラジオ/初期のラジオ番組/マス・メディアとナショナル・イベント/第III章 混沌から秩序へ/1 ラジオは電話である──AT&T、ラジオへ進出す/ラジオとはなにか/「有料放送」の発明/WEAFの開局と「チェーン放送」のはじまり/無線電話からラジオへ/2 山分けのやりなおし──「一九二六年相互特許協定」の成立/テレフォン・グループ対ラジオ・グループ/AT&Tの撤退/NBCの誕生/ラジオ、産業となる/3 混信とパブリック・インタレスト──全米無線会議の展開/ラジオが聴きにくくなってきた/全米無線会議の招集/パブリック・インタレストとはなにか/4 「一九二七年無線法」とFRCの発足/「一九二七年無線法」の成立/「くらげのような委員会」/制度的規律と産業的発達/第IV章 大恐慌による放送産業の確立/1 「暗黒の木曜日」とRCAの台頭/繁栄のバンドワゴン/小春日和の崩壊/RCA、ヘゲモニーを握る/ラジオが受けたインパクト/2 さまざまな可能性/ラジオに魅入られた人々/「誰が、いかにして支払うべきか」/見えない受け手たち/3 「コマーシャル放送」の展開/アメリカの広告/時間を売ります/有料無線電話からコマーシャル・ラジオ放送へ/4 サーノフとペイリー/ネットワークの始原「チェーン放送」/サーノフとNBC/ペイリーとCBS/その他の可能性/5 ネットワークの勃興/ネットワーク加盟契約/CBSの加盟契約/寡占市場の形成/第V章 エーテルの劇場化──番組という文化の形成/1 日々の楽しみたち/ラジオの黄金の日々/インダストリアル・デザインされたラジオ/聴き手たち──「二次的な声の文化」/2 番組という文化コード/「明日、また同じチャンネルで」/ベニー・グッドマンとバッハ/バラエティとソープ・オペラ/エド・マローと放送ジャーナリズムの形成/3 スポンサーの定着/ラジオ広告の発達/スポンサーと広告代理店/第VI章 テレビジョンの到来/1 「テレ+ビジョン」の徴候/電気、テレ・コミュニケーション、テレビジョン/協同する発明家たち/2 テレビジョン標準化をめぐる攻防/テレビジョンを疎外したラジオ/「ラジオ・シティ」はテレビジョンのために/NTSCの成立/3 ラジオからテレビジョンへ/揺籃期と戦争/テレビジョンもコマーシャルになった/ラジオ、ハリウッド、テレビジョン/小窓のついたラジオ/ラジオとテレビジョン/終章 再帰──テクノロジー・メディア・社会/ラジオ・マニアからマイコン・マニアへ/ニュー・メディアは古くからある/移植された日本のメディア/メディアの政治経済的特性/想像力の隠蔽/揺らぎとメディア論の覚醒/連関から融合へ/メディアの生成/註/あとがき/数表/放送メディアの形成をめぐる年表/写真・図版の出所一覧/参考文献/文庫版のための補論
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モルテン
ぷほは
バーニング
Rick‘s cafe
-

- 電子書籍
- ELDEN RING 黄金樹への道【分…
-

- 洋書
- The Jackals