内容説明
“理系の本”をめぐるユニークで熱きメッセージ
ようこそ、みなかワールドへ! 理系研究者を生業としながら、数多の本を読み、新聞やSNSなどさまざまなメディアで書評を打ち、いくつもの単著を出版してきた〈みなか先生〉からの〈本の世界〉への熱きメッセージ。さあ、まずはたくさん本を読もう! 東京大学出版会創立70周年記念出版。
【主要目次】
本噺前口上 「読む」「打つ」「書く」が奏でる “居心地の良さ”
プレリュード――本とのつきあいは利己的に
1 読むこと――読書論
2 打つこと――書評論
3 書くこと――執筆論
第1楽章 「読む」――本読みのアンテナを張る
1-1 読書という一期一会
1-2 読む本を探す
1-3 本をどう読むのか?――“本を学ぶ”と“本で学ぶ”
1-4 紙から電子への往路――その光と闇を見つめて
1-5 電子から紙への復路――フィジカル・アンカーの視点
1-6 忘却への飽くなき抵抗 ――アブダクションとしての読書のために
1-7 “紙” は細部に宿る――目次・註・文献・索引・図版・カバー・帯
1-8 けっきょく、どのデバイスでどう読むのか
インターリュード(1)「棲む」―― “辺境” に生きる日々の生活
1 ローカルに生きる孤独な研究者の人生行路
2 限界集落アカデミアの残照に染まる時代に
3 マイナーな研究分野を突き進む覚悟と諦観
第2楽章 「打つ」――息を吸えば吐くように
2-1 はじめに――書評を打ち続けて幾星霜
2-2 書評ワールドの多様性とその保全――豊崎由美『ニッポンの書評』を読んで
2-3 書評のスタイルと事例
2-4 書評頻度分布の推定とその利用
2-5 書評メディア今昔――書評はどこに載せればいいのか
2-6 おわりに――自己加圧的 “ナッジ” としての書評
インターリュード(2)「買う」――本を買い続ける背徳の人生
1 自分だけの “内なる図書館” をつくる
2 専門知の体系への近くて遠い道のり
3 ひとりで育てる “隠し田” ライブラリー
第3楽章 「書く」――本を書くのは自分だ
3-1 はじめに――“本書き” のロールモデルを探して――逆風に立つ研究者=書き手
3-2 「読む」「打つ」「書く」は三位一体
3-3 千字の文も一字から――超実践的執筆私論
3-4 まとめよ、さらば救われん――悪魔のように細心に,天使のように大胆に
3-5 おわりに――一冊は一日にしてならず……『読む・打つ・書く』ができるまで
ポストリュード――本が築く “サード・プレイス” を求めて
1 翻訳は誰のため? ――いばらの道をあえて選ぶ
2 英語の本への寄稿――David M.Williams et al.,The Future of Phylogenetic Systematics
3 “本の系統樹” ――“旧三部作” から “新三部作” を経てさらに伸びる枝葉
本噺納め口上 「山のあなたの空遠く 『幸』住むと人のいふ」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
tamami
とある内科医
緋莢
あつもり
-

- 電子書籍
- 香月さんの恋する時間 ベツフレプチ(1…
-
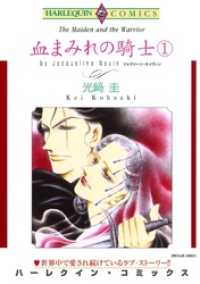
- 電子書籍
- 血まみれの騎士 1巻【分冊】 12巻 …
-

- 電子書籍
- 【SS付き】冒険がしたい創造スキル持ち…
-

- 電子書籍
- 【プチララ】恋と心臓 第61話&62話…





