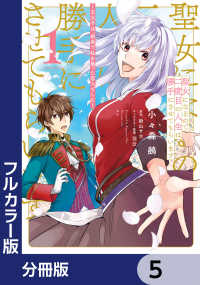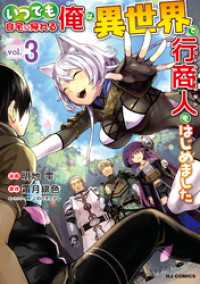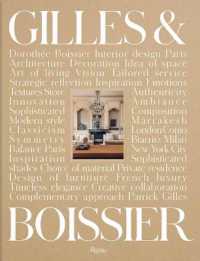内容説明
数十トンもある雲が落ちてこないのはなぜ? 雨粒はどのようにできる? 高原は太陽に近いのになぜ涼しいの? ジェット気流って何? 高気圧や低気圧はなぜできるの? 台風はどうやって発達する?
気象にまつわる素朴な疑問から、気象と天気の複雑なしくみまで、その原理を詳しく丁寧に解説。「しくみがわかる」を重視した入門書です。気象用語の多くを網羅し、気象予報士を目指すスタートにも最適です。
たとえば、下記のような「原理(しくみ)」を解説しています。
・「湿った空気」は重くない
・「赤外線のジャグリング」で気温が決まる
・「気圧のセオリー」でわかる低気圧と高気圧
・「ジェット気流が低気圧・前線を発達させる
本書は、2011年3月に出版され、23刷まで増刷された『図解・気象学入門』の改訂版です。この12年の間、それまではほとんど聞くことのなかった「線状降水帯」といった気象用語が天気予報で盛んに使われるようになりました。「今までと違う」と感じられる異常気象が毎年のように現れ、気象を理解することへの関心はますます高まっているのではないでしょうか。
改訂版は、そのような変化に対応できるよう、わかりやすいと好評であった内容はそのままに、新しい気象用語を加えました。さらにわかりやすくするための修正や補充を行った最新完全版となっています。
1章 雲のしくみ
2章 雨と雲のしくみ
3章 気温のしくみ
4章 風のしくみ
5章 低気圧・高気圧と前線のしくみ
6章 台風のしくみ
7章 天気予報のしくみ
目次
第1章 雲のしくみ
雲が空に浮かんでいられるわけ/温められた空気を上昇させる力は何か/湿った空気は重くない/水蒸気はどう雲の粒に変わるか/雲ができる大気の構造を知る/雲にはどのような種類があるか
第2章 雨と雲のしくみ
雲の粒から雨粒への成長の鍵は何か/日本付近の雨はどのようにして降るか/自分で殖える積乱雲の不思議/豪雨はどのようなときに発生するか
第3章 気温のしくみ
大気を温める「放射」を知る/1日の気温変化はどのように生じるか/気温は緯度と季節によりどう変わるか
第4章 風のしくみ
気圧の差は何によってできるか/地上の風はどのように吹くか/上空に吹く風はどうなっているか/地球規模の風はどうなっているか/大陸と海が生み出す季節風
第5章 低気圧・高気圧と前線のしくみ
温帯低気圧はなぜ発達できるのか/温帯低気圧の発生から消滅まで/いろいろな高気圧のでき方/梅雨はなぜ起こるのか
第6章 台風のしくみ
台風は組織化された積乱雲でできている/台風はどのようにして発生するのか/台風を発達させるしくみ/台風はなぜ日本にやってくるのか
第7章 天気予報のしくみ
天気予報に必要な気象観測/コンピュータはどのように予報を行うのか/いろいろな天気予報
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
nico🐬波待ち中
あねさ~act3 今年1年間は積読本を無くす努力をしたいなぁ。←多分無理🤣
もっぱら有隣堂と啓文堂
特盛