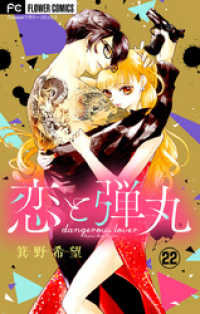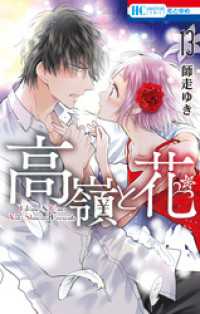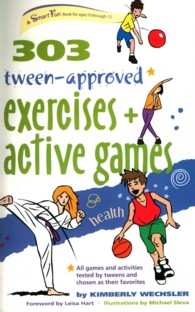内容説明
生物の進化のメカニズムは、自然淘汰のなかで自らが生き残り、子孫を残して遺伝子をつなぐという「利己的」な動機に基づいて説明されることが多い。だとすれば、多くの種で観察される「利他的」な行動は、どのように説明すればよいのだろうか? 本書は、植物学者と動物学者がタッグを組み、その謎の答えに迫る。カギとなるのは「共生」という戦略である。互いの強みを融合し、欠点を補い合いながら自然淘汰に打ち克った生物たちのドラマをお届けする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
67
「利他」「利己」という言葉。そして「共生」という言葉も含めて、考えさせられる。捉え方で、随分、違うものだなあ~と思いながら読んだ。それが、生命の歴史でもあり、まさに、生き残ったものがその結果である。偶然、突然変異の結果が、今のつながる。それは、単に、一生命体だけでなく、種、或いは社会にもつながる視点。タイトルにある生物学の中に、人も入る。科学の書でもあり、哲学の書でもあると思う。2023/10/17
よっち
31
利己的な動機に基づいて、自然淘汰される中を生き残ってきた生物進化。そこで多くの事例が観察される利他的な行動を植物学者と動物学者がタッグを組み、カギとなる「共生」という戦略をもとにその謎の答えに迫る1冊。なぜ利他的な行動というものが生まれたのか。進化に使えるものは何でも使ってきた生物たちが、共生することで見出した活路。昆虫と植物の華麗な騙し合い、植物と菌のコミュニケーション、腸内細菌との共生から見た超生命体としての人類など、共生することは必ずしも利他的行動ではない生物たちの営みをなかなか興味深く読みました。2023/08/15
ひめぴょん
20
植物学者と動物学者による共生などを例にして生きものの相互関係を知る本。生き物が存在し続けるためには自分だけというやり方では上手くいかない。持ちつ持たれつというところか。バランスが崩れると、人間同士の関係もうまくいかなくなる。以下は文中で気になった言葉。 利他的行動のほうが、利己的行動よりも集団としてのメリットが大きい。 進化に必要なのは遺伝であり、遺伝子を保持する個体自身は「遺伝子の乗り物」(ドーキンス) 利他性に関わるオキシトシンは子供や他の動物の世話をすることによっても分泌される。「育てる行為」は面倒2023/09/07
テツ
16
タイトルにある『利他』ではなく『共生』についての内容。生物の目的は自らの種がこの地上で唯一の種になることではなく、遺伝子を受け継ぎ続けること。そのためにまず自らを生き延びさせることが先決だし、その途中で他の種に利益を与えても構わない。別に他種を蹴落とすことが目的ではないのだから。「どれかが、だれかが、遙か未来に至ればそれで構わない」という執念が生命には備わっているように錯覚してしまうな。共生も競争もそのための手段にすぎない。誰でもいいから生き延びろ。2024/01/18
紡ぎ猫
13
単なる科学の説明だけにとどまらず、そこから、人間社会とは何か、生きるとは何かみたいなことを考えるよう促してくれる。結局、生物は利己的でもあり利他的でもあり、その両方があったからここまで進化してきたのかなと思う。ある集団の中で協調的な人間は70%、協調的でない人間は30%だという。それが逆じゃなくてよかった。2023/09/22



![グランドゼロ [GOD‐GUN世郎<グランドギア>]改題 HIROSUKE KIZAKI MEMORIAL EDITION ビームコミックス](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1156935.jpg)